「なぜこの曲のタイトルは“JANE DOE”なのか?」そう感じた方も多いのではないでしょうか。
宇多田ヒカルと米津玄師の共演によるこの楽曲には、“名無しの存在”を意味する言葉の裏に、深い物語と象徴性が隠されています。
本記事では、その意味を丁寧に読み解きながら、歌詞に込められた比喩表現や映画『チェンソーマン レゼ篇』とのつながりを掘り下げていきます。
この記事を読むと
- 「JANE DOE」の語源や文化的背景が理解できます
- 歌詞に潜む象徴表現(硝子・血・金魚・林檎など)を解釈できます
- 映画『レゼ篇』との物語的リンクを把握できます
- 宇多田ヒカルと米津玄師の歌唱構造と役割分担が見えてきます
- 匿名性が象徴する“孤独”というテーマを深く考察できます
この記事を読むことで、歌詞の背後にある世界観と物語の本質に、より深く触れることができるでしょう。
本記事は情報量が多いため、気になるところからお読みいただけるよう、目次を設けています。
目次の見出しをタップまたはクリックすると、該当箇所へジャンプします。
『JANE DOE』は、映画のエンディングを彩る静かな余韻の一曲ですが、対になるオープニングテーマ『IRIS OUT』もまた重要な意味を持っています。2曲を対比することで、作品全体のテーマがより深く見えてきます。
→ 『IRIS OUT』歌詞考察はこちら
『JANE DOE』のタイトルが意味するものは?レゼと“名無し”に込められたメッセージ
『JANE DOE』というタイトルには、英語の慣用表現以上の重みがあります。
このセクションでは、その文化的な背景と、レゼというキャラクターがどう結びついているのかを見ていきましょう。
「名前を持たないこと」が示すのは、単なる匿名性ではなく、誰にも知られずに生きる孤独や痛み。
それがレゼの存在とどう重なっているのかを丁寧に掘り下げていきます。

『JANE DOE』って、ただの名前じゃなくて何か特別な意味があるんですか?



はい、「JANE DOE」は英語圏で「身元不明の女性」を指す仮名です。単なる匿名性ではなく、社会から存在を認識されない孤独や、名前のない痛みを象徴しており、まさにレゼというキャラクターの境遇と重なります。
▼『JANE DOE』公式MV
歌詞の解釈に入る前に、一度視聴しておくと理解が深まります。
米津玄師, 宇多田ヒカル Kenshi Yonezu, Hikaru Utada – JANE DOE
“JANE DOE”の本当の意味とは?英語圏文化とレゼの共通点
“JANE DOE(ジェーン・ドウ)”は、英語圏で身元不明の女性を指すときに使われる仮名です。
とくに医療や司法の分野で用いられ、「名を持たない存在」の象徴として知られています。
この意味は『チェンソーマン』に登場するレゼの在り方と深くつながっているんです。
彼女は“レゼ”と名乗りますが、それが本名かどうかは最後まで明かされません。
その姿はまさに“JANE DOE”であり、観る者に「正体はわからないけれど、強く惹かれる」という印象を与えるでしょう。
タイトルにこの言葉が選ばれたのは、レゼが抱える孤独や無名性が、物語そのものとリンクしているからかもしれません。



“JANE DOE”ってどこで使われる言葉なんですか?



“JANE DOE”は英語圏で、身元不明の女性を指すときに使われる仮名です。医療や司法の現場で使われることが多く、「名前を持たない存在」の象徴とされています。
“名無しの少女”レゼが背負う孤独と痛み:歌詞と映画のリンクを考察
レゼは本名を語らないまま物語を終えます。
彼女の素性についてはいくつかの事実が明かされますが、“レゼ”という名が本名かどうかは最後まで不明のままです。
その“名無し”という状態が彼女の孤独を際立たせています。
そしてその痛みは、『JANE DOE』の歌詞にもはっきり現れているんです。
硝子の上を裸足のまま歩く
血が流れて落ちていく
(出典:楽曲『JANE DOE』 歌:宇多田ヒカル・米津玄師/作詞・作曲:米津玄師)
「硝子の上を裸足のまま歩く」という描写は、美しくも傷つきやすい生き方を象徴していて、その痛みが「血が流れて落ちていく」という言葉でさらに強調されます。
誰にも名前を呼ばれず、存在を知られないまま生きる苦しみ。
レゼというキャラクターが背負うその重さは、歌詞と映画の両方で共鳴しています。
“JANE DOE”というタイトルは、そんな存在に向けた静かな祈りのようにも聞こえるんです。



レゼが“名無し”であることは、作品の中でどんな意味を持つんですか?



レゼが本名を語らないまま物語を終えることで、彼女が「名を持たない存在=JANE DOE」として描かれています。その孤独や痛みが、楽曲の比喩や歌詞の構成と重なり合うように設計されているのです。
歌詞に隠された“比喩”の読み解き方:宇多田ヒカル×米津玄師の視点と感情
『JANE DOE』の歌詞には、表面的な感情だけでは読み解けない深い比喩がたくさんあります。
硝子や血、金魚、林檎といったモチーフが、感情や心理の揺れを表現しているんですね。
さらに、宇多田ヒカルと米津玄師がそれぞれ異なるパートを歌うことで、視点の違いが楽曲に深みを与えています。
ここでは、歌詞に込められた象徴と感情の構造を丁寧に見ていきましょう。



比喩って難しそうですが、どこに注目すれば意味がわかるんですか?



ポイントはモチーフに注目することです。「硝子」「血」「林檎」などは感情や状況の象徴で、表面だけでなく、その背後にある心理描写を想像することで理解が深まります。
「硝子」「血」「金魚」「林檎」の意味を徹底考察:歌詞に込められた深層心理
この曲に登場する「硝子」「血」「金魚」「林檎」といったモチーフは、それぞれが登場人物の内面を映し出す象徴となっています。
「硝子の上を裸足のまま歩く」は、危うさや繊細な痛みを暗示する比喩なんですね。
「血」は、その痛みが現実のものとして滲み出ていることを示唆しています。
「金魚」は水中で自由に泳ぐ存在ですが、「放たれていく」という表現があることで、制御できない運命や心の不安定さを描いているとも取れます。
「林檎」は、旧約聖書でいう“禁断の果実”のように、魅惑と罪の象徴として扱われているように思えます。
こうした比喩を読み解くことで、表現されている心理の深さが一気に見えてくるんです。



それぞれのモチーフには、どういう意味があるのでしょうか?



「硝子」は繊細な心、「血」はその傷、「金魚」は不安定な運命、「林檎」は魅惑と罪の象徴です。どれも登場人物の感情や背景を表しており、歌詞全体に深みを与えています。
宇多田と米津、それぞれの“視点”に込めた想いとは?対照的な歌詞構成の秘密
『JANE DOE』のもう一つの大きな魅力は、宇多田ヒカルと米津玄師が交互に歌う構成です。
それぞれが異なる視点から物語を語っていて、それが楽曲に奥行きを与えているんです。
宇多田のパートは、切なさや願い、時間の中に取り残されたような感情が中心。
米津のパートでは、「錆びたプール」「迷子」など過去や記憶の断片が描かれていて、少し混沌とした雰囲気があります。
この“すれ違い”の構成は、レゼとデンジの関係性ともリンクしていて、近づきながらも決して交わりきれないふたりの姿を表しています。
作詞作曲を手がけた米津玄師が、自身も歌唱に参加しつつ、楽曲の重要なパートを宇多田に託したことも、その対比構造をより明確にするためだったのかもしれませんね。
実際、米津自身「この曲は自分ではなく、宇多田さんしかいない」と制作過程で確信を抱き、オファーに至ったと語っています。



2人のパートはどんなふうに違うんですか?



宇多田ヒカルのパートは切なさや願い、米津玄師のパートは喪失感や記憶の断片を表現しています。この対照的な視点が、物語のすれ違いを象徴しています。
issyによる『チェンソーマン レゼ篇』の深層考察:「JANE DOE 歌詞 考察」


『JANE DOE』って曲、初めて聴いたとき「ただのエンディング曲じゃねぇぞ…」って感じた人、結構いるんじゃないかな?
実はこれ、レゼってキャラの存在そのものを歌ってるってワケ!
名前を呼ばれず、誰にも気づかれず、それでも心を揺さぶる“名無し”の少女。
そんな彼女に対して、米津玄師と宇多田ヒカルがまるでラブレターみたいにメッセージを贈ってるんだよな。
この記事では、歌詞に込められた比喩や構成、映画とのリンクを通して、“JANE DOE=レゼ”というテーマを深掘りしていくよ!
“JANE DOE”という名前が示す「名もなき痛み」
“JANE DOE”ってのは、英語圏で「身元不明の女性」に使われる仮名なんだよ。
病院や警察とかで、名前のわからない遺体や患者に付けられるやつ。つまり、「誰にも名前を呼ばれなかった人」ってことになる。
これ、まさにレゼと重なるんだよな。
作中で彼女は“レゼ”って名乗ってるけど、それが本名かどうかは明かされない。
スパイとしての役割を担い、物語の対立軸に立つ存在でもある、でも一人の少女としての姿もある。
そんな“正体不明”の存在として、彼女は物語をずっと“名無し”のまま駆け抜けていくわけ。
裸足で硝子の上を裸足のまま歩く
(出典:楽曲『JANE DOE』 歌:宇多田ヒカル・米津玄師/作詞・作曲:米津玄師)
歌詞にある「裸足で硝子の上を裸足のまま歩く」って描写も、ただの痛々しい比喩じゃなくて、“名無しのまま生きる苦しさ”をそのまんま象徴してる感じなんだよな。
誰にも知られず、名を持たず、それでも「ここにいる」って叫び続ける存在。そこに「JANE DOE」ってタイトルを被せるセンス、マジでしびれるってワケ!
→レゼ=誰にも知られない痛みの象徴って見方ができる。
「比喩の洪水」に隠された心理:歌詞のモチーフ徹底分解!
次に注目したいのが、歌詞に散りばめられたモチーフたち。
「硝子」「血」「金魚」「林檎」って、どれも意味深すぎるだろってやつ。しかも全部、レゼの内面とガッツリつながってるんだよな。
錆びたプールに放たれていく金魚
靴箱に隠された林檎
(出典:楽曲『JANE DOE』 歌:宇多田ヒカル・米津玄師/作詞・作曲:米津玄師)
- 硝子&血:この組み合わせは、繊細で壊れやすい心をそのまま表してる。ガラスの上を裸足で歩くなんて、もう「傷ついても進むしかない」って覚悟の表れじゃん。そしてその痛みが「血」として滲むことで、見えない苦しみが現実として可視化されるってワケ。
- 金魚:「錆びたプールに放たれていく金魚」っていう描写は、一見自由そうだけど、実は逃げ場のない存在を表してる感じ。レゼもまた、自由を求めてるのに、どこにも逃げられないっていう構図とリンクしてるよな。
- 林檎:「靴箱に隠された林檎」って表現、もう完全に“禁断の果実”の匂いがするよね。これは恋や欲望、そして罪悪感の象徴でもあって、レゼの二面性――日常と非日常を行き来する彼女の立ち位置を表してるとも読める!
こういうモチーフって、ただの詩的な言葉遊びじゃなくて、全部がレゼの感情や状況を可視化する装置になってるんだよ。
しかもめちゃくちゃ繊細で計算されてるから、読み解けば読み解くほど深みが出てくる!
→この曲は、比喩を通してレゼの心理を“音楽で描写”してると考えられるね。
米津と宇多田の“対話形式”が描く、レゼとデンジのすれ違い
『JANE DOE』の構成がまた天才的でさ、米津玄師と宇多田ヒカルが交互に歌ってるんだけど、これがただの掛け合いじゃなくて、「視点の違い」が表現されてるんだよな。
もう行かなきゃ
会いにきて(出典:楽曲『JANE DOE』 歌:宇多田ヒカル・米津玄師/作詞・作曲:米津玄師)
- 宇多田パート:どこか切なさと諦めが滲んでる。「もう行かなきゃ」ってフレーズ、まんまレゼの別れの言葉に聞こえるし、「会いにきて」っていうのは、最後の願いとして心に刺さるんだよね。
- 米津パート:逆にこっちは、記憶の断片みたいな描写が続いてて、「失った誰か」を探してるような視点に思える。まるでデンジがレゼの幻影を追いかけてるような感じ。
つまりこの曲、「レゼ視点の別れ」×「デンジ視点の喪失」っていう、映画とリンクした構図になってるんだよな。
最後にもう一度「会いにきて」が繰り返されることで、希望と未練が入り混じったラストになるのもエモすぎるってワケ!
→楽曲構成が、キャラ同士の感情のすれ違いとリンクしているという見方ができる。
最後に:この曲が語る“レゼの正体”とは
まとめると、『JANE DOE』はレゼという“名無しの少女”の声であり、同時に彼女を想う誰かの心の声でもある。
だからこそ、米津と宇多田という“ふたり”で歌う意味があるんだよね。
歌詞はめちゃくちゃメタファーだらけだけど、そこに込められた想いはストレートで、心にズドンとくる。孤独、痛み、すれ違い。でも、その中に確かにあった「好きだった」という気持ち。
これこそが『レゼ篇』のコアなんだよな。
レゼは“JANE DOE”として物語から姿を消していく。
でも、この曲は彼女の存在が「確かにここにいた」と伝えてくれる祈りのような歌なんだ。
名前も知られず、誰にも覚えられない…そんな存在にも意味があるって、そう言ってくれてる感じ。
→『JANE DOE』は、レゼという“名無しの少女”への追悼と祝福を込めた、静かな祈りの歌と考えられるね。
「名前がない」ってだけで、こんなに切なくて深いテーマになるとはな…。レゼには“名乗ることすら許されなかった”悲しみがある。
でもその分、この曲がしっかりと彼女の存在を刻んでくれてるんだよな。映画観た後にもう一回聴いてみ?泣くぜマジで。
この考察を書いたのは、アニオタ歴20年以上の陽キャアニメブロガー・issy(いっしー)です。マイナーな名作を見つけて語るのが大好きで、「アニメは人生の教科書」という思いで作品の魅力を発信しています。
よくある質問
- 『JANE DOE』というタイトルの意味は何ですか?
-
『JANE DOE』は英語圏で「身元不明の女性」を指す仮名です。名前を持たない存在の象徴であり、物語ではレゼの正体不明性や孤独と重ねて解釈されています。
- 歌詞に登場する「硝子」「血」「金魚」「林檎」は何を象徴していますか?
-
「硝子と血」は繊細さや痛みを、「金魚」は不安定な自由や運命を、「林檎」は禁断や誘惑を示すとも解釈されています。比喩を通してレゼの心情が描かれていると考えられます。
- 宇多田ヒカルと米津玄師が交互に歌う構成にはどんな意図がありますか?
-
二人の歌声は異なる視点を表しているとされます。宇多田は別れの切なさを、米津は記憶や喪失感を描き、レゼとデンジのすれ違いを音楽的に表現していると解釈できます。
- レゼと『JANE DOE』はどのように結びついていますか?
-
レゼは本名を明かさず“名無し”として描かれます。その姿が「JANE DOE=名を持たない存在」と重なり、楽曲全体が彼女の孤独や存在の儚さを映していると受け取られています。
JAEN DOE 歌詞の意味を考察まとめ
この記事では、『JANE DOE』というタイトルとその歌詞に込められた意味を、キャラクター「レゼ」の視点から丁寧に読み解きました。
- “JANE DOE”は「名無しの存在」を意味し、レゼの正体不明性と孤独を象徴している
- 歌詞に登場する「硝子」「血」「金魚」「林檎」などの比喩が、レゼの内面世界を視覚化
- 宇多田と米津の対照的な歌唱パートが、レゼとデンジのすれ違いを音楽で表現
- 曲全体が、“名を呼ばれなかった少女”レゼへの静かな祈りとして機能している
『JANE DOE』は単なる挿入歌ではなく、レゼというキャラクターの本質を浮き彫りにする象徴的な作品です。
ぜひ歌詞と映像を重ねながら、その深層に込められたメッセージを味わってみてください。



『JANE DOE』の歌詞ってすごく抽象的でしたけど、結局どんな意味があったんですか?



この曲は、レゼという“名無しの少女”の存在と心の痛みを象徴しています。歌詞に込められた比喩や視点の対比が、彼女の孤独や正体不明性を浮き彫りにし、まさにレゼという存在を祈るように描いているのが特徴です。


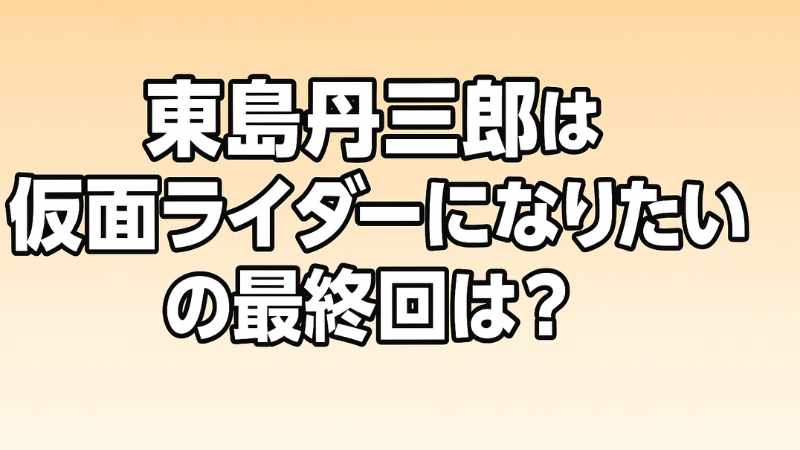
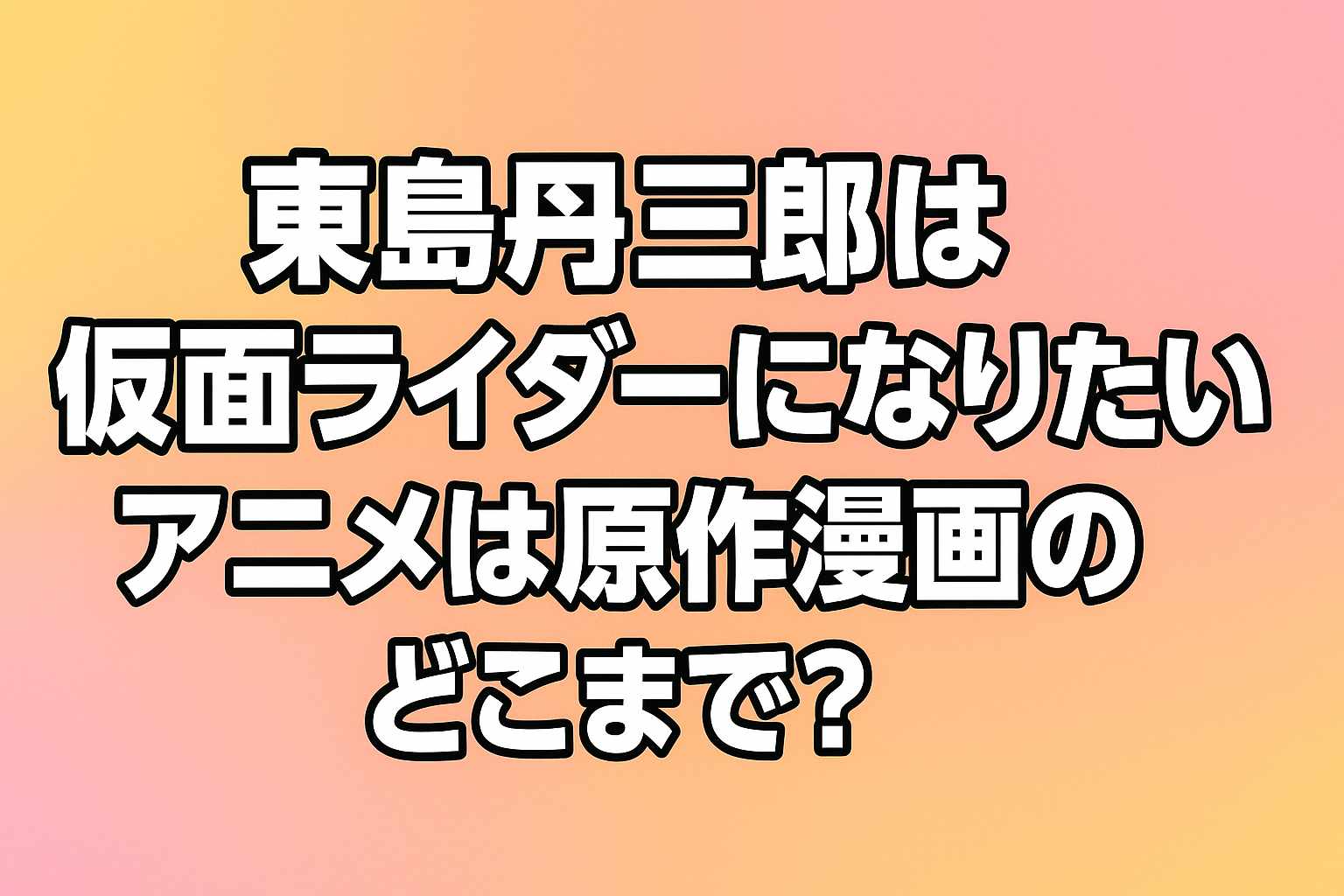
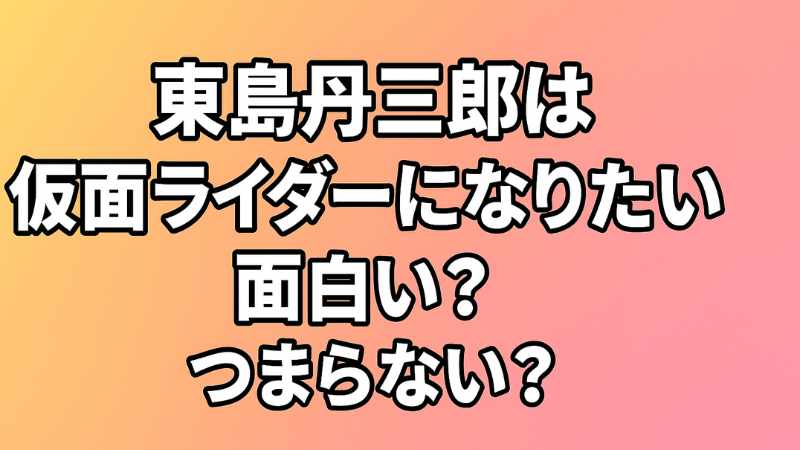
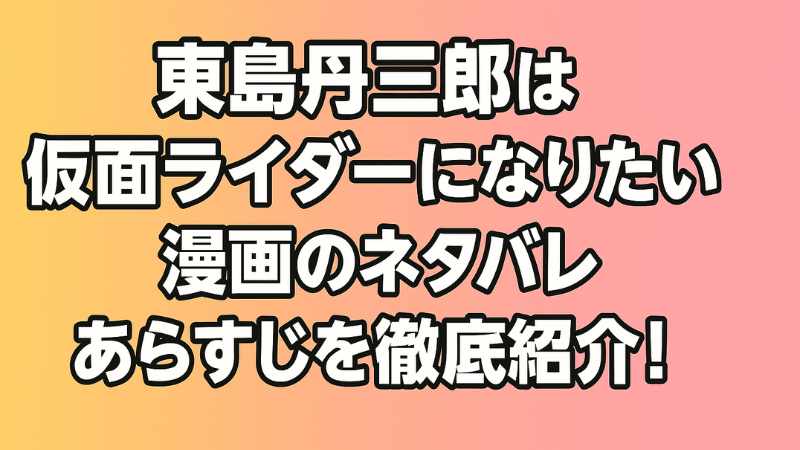

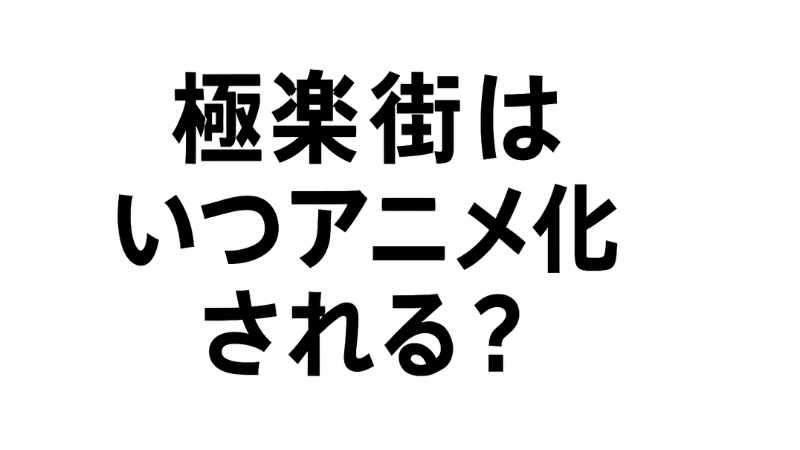
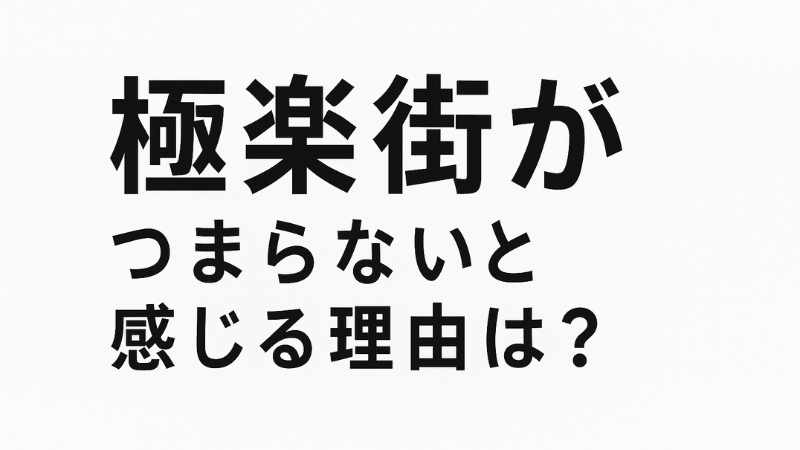

コメント