『高杉さん家のおべんとう』が「気持ち悪い」と言われる理由を解説。『うさぎドロップ』との共通点やSNSの声をもとに考察します。
「家族のあたたかい物語だと思っていたのに、なぜか心に残るひっかかり──」
『高杉さん家のおべんとう』を読み終えた多くの読者が、終盤の展開に違和感や戸惑いを抱いています。
親子のようだった関係が、恋愛へと変わっていく。
その描かれ方に、なぜ「気持ち悪い」と感じる人がいるのでしょうか。
この記事では、作品への否定的な反応の背景を、登場人物の関係性や物語の流れ、そして読者の受け取り方の視点からひもとき、SNSやレビューの声も交えて考えていきます。
この記事を読むと
- なぜ「気持ち悪い」と感じる読者が多いのかがわかる
- 終盤の恋愛展開に対する拒否反応の背景が理解できる
- SNS・レビューに見られる賛否の傾向が整理できる
- 『うさぎドロップ』との比較による位置づけが見える
- 作者の意図や物語の深層的なテーマを再解釈できる
この記事を読むことで、あなたの中にある「もやもや」の理由が少しでも見えてくるきっかけになれば幸いです。
『高杉さん家のおべんとう』が「気持ち悪い」と言われる背景
『高杉さん家のおべんとう』は、家族のつながりや成長を描いたハートフルな作品として親しまれてきましたが、終盤の展開をめぐって「気持ち悪い」という声も少なくありません。
なぜ一部の読者が違和感や不快感を抱いたのか――その背景には、作品が踏み込んだ“家族と恋愛”の曖昧な境界線があります。
この章では、物語の終盤に見られる恋愛要素への反発や、倫理的・心理的に引っかかるポイントを丁寧にひも解いていきます。

「気持ち悪い」と感じる読者が多いのは、具体的にどういう理由からなんですか?



作品終盤で“家族のような関係”から“恋愛関係”に変わる展開があったため、読者の倫理観とズレが生まれたのが原因です。このテーマの曖昧さが大きな論点となっています。
終盤で恋愛に変わる展開への拒否感
多くの読者が強く違和感を覚えたのが、終盤で主人公・高杉と久留里の関係が恋愛へと進展していく描写です。
序盤から中盤にかけては、お弁当作りを通じて築かれる疑似家族のような関係性が中心で、読者もその温かさに自然と共感していました。
最終巻で久留里から高杉への告白があり、それまでの“家族的な絆”が“恋愛関係”に変化する展開が物議を醸します。



家族的な関係から恋愛に変わるって、そんなに違和感があるものなんでしょうか?



読者は高杉と久留里の関係を“家族のようなもの”として見ていたため、突然の恋愛展開は裏切りのように感じられたのです。これが強い拒否感の背景です。
特に問題視されたのは、久留里が中学生時代から高杉に世話されてきたという育成関係の延長上に恋愛が描かれた点です。
この構造に対して、「うさぎドロップと同じ構造で無理」「なぜ家族のままではいけなかったのか」といった声が多く見られました。
作中では、温巳が久留里との関係に踏み出す際に“ゴムの心配”を口にする描写がある。
このセリフに対して、レビューやSNSでも強い拒否反応が多く見られた、唐突な恋愛へのシフトが“生理的に無理”というレベルで受け入れられなかったことが読み取れます。
物語の完成度とは別に、「終盤の方向転換」によって一気に評価が変わってしまった――この点こそが、本作の評価を分ける最大のポイントとなっています。
保護者と未成年の関係が生むモヤモヤ
『高杉さん家のおべんとう』における最大の論点の一つが、「保護者と被保護者の関係性を超えて恋愛に発展することの倫理的な是非」です。
久留里が中学生の頃から高杉に育てられてきたという事実がある以上、読者の目には「育成→恋愛」という文脈が強く映ります。
この構造は現実社会では明確に“越えてはいけない境界線”と認識されているため、フィクションであっても抵抗感を覚える人が多いのです。



保護者と被保護者の関係が続いた後に恋愛へ発展する場合でも、やっぱり倫理的な問題があるんですか?



はい、たとえフィクションでも“育ててきた相手との恋愛”という構造に倫理的な抵抗を感じる人は多くいます。このため読者からは強いモヤモヤが生まれました。
特に、高杉が久留里の保護者としての責任を全うしつつ、ラストで恋愛感情を見せる描写は「どこか不自然」「誠実に見えない」といった批判につながりました。
作中では血縁関係がないことも明かされ、恋愛を成立させるロジックとして機能しますが、それでも「擁護には無理がある」と感じる層が一定数います。
このテーマに関しては、『うさぎドロップ』と比較されることも多く、「またこのパターンか…」という疲弊感すら見られるのが実情です。
作者としては家族と恋愛の狭間にある“曖昧な関係”を描こうとした意図があったとしても、現代の倫理観や読者の感性と大きくズレてしまったことは否めません。
読者が違和感を覚える3つの理由
『高杉さん家のおべんとう』に対して違和感を抱く読者の声には、いくつかの共通したパターンがあります。
なぜ「気持ち悪い」と感じたのか――その理由は、恋愛要素の有無だけではなく、物語の進め方や心理描写の積み重ね方にも潜んでいるようです。
この章では、読者の反応をもとに代表的な3つの“ひっかかりポイント”を取り上げ、作品に内在する構造的な違和感の正体を探っていきます。



「気持ち悪い」と感じた理由は恋愛要素だけじゃないんですか?



その通りです。読者の違和感は、恋愛展開そのものよりも、描き方や物語の構造にある“積み重ね不足”や心理的なギャップから来ていることが多いです。
読者が心情的に受け入れにくい部分
最初に挙げられるのが、「どうしても気持ちの整理がつかない」という心情面での拒否反応です。
序盤から中盤にかけて描かれていたのは、年齢も立場も違うふたりが少しずつ信頼を築き、家族になっていく過程でした。
だからこそ、読者は高杉に“父性的な愛”や“保護者としての責任感”を重ねて見ていたわけです。



なぜ読者は心情的にこの関係を受け入れにくいと感じたのでしょうか?



父性や恩人として見ていた対象が急に恋愛関係になることで、読者は「裏切られた」と感じてしまったのです。この感情のギャップが大きな拒否感につながっています。
そんな中で終盤の恋愛展開は、「裏切り」にすら感じられてしまいます。
特に久留里の視点から見ると、高杉は“恩人”であり“親代わり”だった存在です。
その相手に恋愛感情を抱く流れには、共感よりも困惑が先に立ったという声が多く聞かれました。
現実では“親のような存在に恋をする”というのは一般的ではありませんそれがごく自然に描かれてしまったことで、違和感を覚えたのかもしれません。
加えて、感情の移り変わりに説得力が欠けていた点も、読者のモヤモヤを増幅させた一因になっています。
物語の進み方が急すぎると感じる部分
次に目立つのが、ストーリー展開の“急さ”に対する指摘です。『高杉さん家のおべんとう』は、日常のちょっとした出来事を丁寧に描く、スローペースな作品として親しまれてきました。
だからこそ、最終巻でいきなり「付き合ってください」と恋愛関係が明示される展開には、多くの読者が置いてきぼりを感じたようです。



物語の展開が急すぎるって、そんなに違和感を持たれるポイントなんですか?



はい、特にゆったりとした日常描写が続いていた作品では、急な展開は読者の没入感を損ねます。恋愛へのシフトに説得力が欠けたと感じる読者が多かったのです。
レビューでも、「4年間会ってなかったのに、いきなり付き合うのは唐突すぎる」「伏線がなかったとは言わないけど、あまりにも早かった」という声が複数見られました。
恋愛に移行するだけでなく、その背景となる心理描写や内面の葛藤がもっと丁寧に描かれていれば、読者の納得感も変わっていたかもしれません。
まるで終盤で“別の作品”になったかのようなスピード感のある変化は、それまでの空気感を壊してしまい、「気持ち悪さ」につながったと考えられます。
大人と子どもの関係が越えてはいけない境界
最後に、多くの読者が敏感に反応したのが、「倫理的なラインを越えてしまったのでは?」という懸念です。
いくら血縁関係がないとはいえ、久留里は中学生の頃から高杉に育てられてきました。
現実であれば“保護者と未成年”という関係は非常にデリケートであり、恋愛へと発展することには社会的なタブーがつきまといます。



血縁がなくても、育成関係からの恋愛ってやっぱりタブーに感じるんですか?



はい、多くの読者にとって“育てた相手と付き合う”という構造そのものに違和感があり、倫理的に踏み込んではいけない領域と感じられたようです。
読者が「これはフィクションだから」と割り切れなかったのは、その境界線があまりに無造作に越えられたように見えたからかもしれません。
作中では、久留里が成人してからの関係として描かれていますが、それまでの育成期間がある以上、積み重ねがそのまま恋愛感情に直結してしまう構図は危うく映ります。
『うさぎドロップ』と同様、この“育てる側と育てられる側”という関係性のゆがみが読者にモヤモヤを残し、作品全体への評価にも大きく影響を与えたのです。
SNSやレビューに見る共感と反発の声
『高杉さん家のおべんとう』の終盤展開をめぐって、SNSやレビューサイトではさまざまな意見が飛び交いました。
とくに最終巻が発売されたタイミングでは、「どうしてこうなった?」「やっぱりこの流れか…」といった感想が多く、議論はヒートアップ。
登場人物やテーマに対する評価が分かれる中で、読者たちは共感と反発を繰り返していたのです。
この章では、SNSで見られた「自分だけじゃなかった」と安心する共感パターンや、擁護派と否定派の意見の食い違い、その背景を詳しく見ていきます。



SNSではどんな反応が多かったんでしょうか?



終盤の恋愛展開に対し、「違和感があったのは自分だけじゃなかった」と安心する共感の声や、「やっぱり無理」という否定派の意見が目立ちました。賛否がくっきり分かれたのが特徴です。
「自分だけじゃなかった」と安心する共感パターン
終盤の恋愛展開に「気持ち悪い」と感じた読者の多くが、まず自分の感覚に不安を抱えていました。
「自分が過剰に反応しているのかな…?」と戸惑いながら、SNSやレビューをのぞいたところ、同じような違和感を持つ人の声に出会い、「自分だけじゃなかった」と安心したという声が目立ちました。



読者同士が共感し合ったことで、どんな影響があったんでしょうか?



「自分もモヤモヤしていた」と感じた人が共感し合うことで、読者同士の安心感や、作品への客観的な分析につながりました。共感の広がりが読者の理解を深めたとも言えます。
この共感の広がりは、「家族のように描かれていた二人が恋人になる」ことへの本能的な抵抗感と深く関係しています。
「ハルがゴムの心配をしてたのが無理だった」「なぜ恋人になる必要があったのか」など、唐突な恋愛描写に拒否感を示す声が続出。
こうした反応からは、読者が“家族のような関係性”を大切にしていたことがよくわかります。
「うさぎドロップも苦手だったからやっぱり無理だった」というコメントも多く、似たような構造を持つ物語への拒絶感が一定層にあることが浮き彫りになりました。
これらの声は、単なる感想にとどまらず、現代の読者が持つ倫理観や関係性への理想を映し出しているともいえるでしょう。
擁護派と否定派の意見の違いとその背景
SNSやレビューでは、「よかった」「受け入れられない」といった二極化した反応が顕著に現れています。
その違いは、物語の受け取り方やフィクションに対する価値観の差に根ざしているようです。



擁護派と否定派では、どんな点で意見が分かれたのでしょうか?



擁護派は「成人後の恋愛だから問題ない」とする一方、否定派は「育てた相手との恋愛は構造的に無理」と捉えました。倫理観とリアリティへの感覚の差が分断の原因です。
擁護派の意見として多かったのは、「久留里が成人してからの関係なので問題ない」「あくまでフィクションとして楽しんでいる」という立場。
「ふたりが幸せになるなら形にこだわらなくてもいい」「これまで見守ってきたからこそ納得できる結末だった」という声も見受けられました。
否定派は「保護者が恋愛対象になる構造が根本的に受け入れられない」「現実では許されない関係を美化しているようで気持ち悪い」といった倫理面からの反発が強く見られます。
中には「“炎上 なぜ”と検索したくなった」という声もあり、現代の感覚と作品の描写が乖離していた印象を受けた人も少なくありません。
この意見の分断は、「フィクションにどこまでリアルさを求めるか」という感覚の違いに起因しているといえます。
物語の自由度を尊重するか、それとも現代社会の倫理観との整合性を重視するか。その立ち位置の差が、評価を大きく分けたポイントなのです。
『うさぎドロップ』との比較で見える共通点と違い
『高杉さん家のおべんとう』が終盤で見せた展開に、読者の多くは『うさぎドロップ』を連想しました。
どちらの作品も“育成から恋愛へ”という似た構造を持っており、そのラストで賛否を大きく分けています。
とくに倫理的な違和感を抱いた読者にとっては、『うさぎドロップ』の「衝撃の結末」が記憶に新しく、それが本作の評価にも影響を与えているようです。
この章では、両作品の共通点と相違点に注目し、なぜ読者の反応がここまで似通っているのかを探ってみましょう。



『高杉さん家のおべんとう』と『うさぎドロップ』って、そんなに似ているんですか?



はい、どちらも“保護者が育ててきた相手と恋愛関係になる”という構造が共通しており、終盤の展開に強い既視感を覚える読者が多かったのです。
年齢差や関係性から恋愛に移る点の共通性
『高杉さん家のおべんとう』と『うさぎドロップ』の共通点としてまず挙げられるのが、「保護者として関わってきた相手と最終的に恋愛関係になる」という構造です。
どちらの物語も、序盤では擬似的な親子関係や、家族のようなあたたかい絆が中心に描かれています。
そうした関係性に読者が共感し、愛着を持ち始めたところで恋愛に切り替わるため、「そういう話だったの?」という戸惑いが生まれてしまうのです。



どちらも最初は親子のような関係だったのに、最後に恋愛になるという点が問題なんですか?



そうです。読者は“家族”としての関係を期待していたため、恋愛への転換が裏切りのように映ってしまい、大きな拒否感を生んだのです。
『高杉さん家のおべんとう』では、久留里が中学生から高校生、そして大学生へと成長していく過程が描かれており、恋愛に至る時点ではすでに社会人になっています。
時間的な経過をきちんと踏まえてはいるものの、“育てた相手と付き合う”という構図そのものに、読者は『うさぎドロップ』と同じ“既視感”を覚えたのです。
とくに問題視されたのは、恋愛に至るまでの心理描写や倫理的な葛藤が表層的に見えてしまった点でした。
結果として、似た構造の作品として同様の拒否反応を引き起こすことになったと考えられます。
読者が拒否反応を示す境界線はどこか
この2作品を比較するうえで重要なのが、「どのラインを越えると無理だと感じるのか?」という心理的な境界線です。
『うさぎドロップ』では、養育していた幼児が成長し恋愛に発展するという展開が、唐突であると同時に“踏み越えてはならない線”を越えたと感じた読者が多くいました。



心理的に受け入れられるラインって、そんなに明確にあるものなんですか?



読者の多くは“保護者と恋愛”の境界に敏感で、フィクションであってもそのラインが曖昧だと強く反発します。リアルな描写であればあるほど違和感も増します。
一方『高杉さん家のおべんとう』は、対象が中学生からスタートし、成長したのちに恋愛関係に移行します。
この点で“恋愛可能な年齢に近づいている”とはいえ、やはり「育ててきた相手と恋愛する」という構造が残るかぎり、拒否感は避けられません。
さらに、『高杉さん〜』のほうが日常描写がリアルで丁寧なぶん、「現実にもありえそう」という生々しさが強調され、「リアルでやられたら無理」と感じた人が多かったようです。
このように、倫理的な緊張感の高いテーマに対して、境界線の描き方が曖昧だったことが、読者の“気持ち悪さ”につながっていったのです。
作者がこの物語で描こうとしたこと
『高杉さん家のおべんとう』は、単なる家族ドラマでも恋愛漫画でもなく、「人と人とのつながりとは何か?」という根源的な問いを描いた作品です。
特に終盤の展開においては、家族と恋愛のあいだにある曖昧な感情や関係性が大きなテーマとなっており、読者にさまざまな感情を呼び起こします。
ここでは、作品にちりばめられた象徴的なモチーフや、作者が込めたメッセージに焦点を当ててみましょう。



この作品で作者は、結局何を一番伝えたかったんでしょうか?



作者は「人と人とのつながりのかたち」や「血縁を超えた絆」のあり方を描こうとしていたと考えられます。その象徴が“お弁当”や“地理学”です。
地理学とお弁当が象徴する家族のつながり
作中で何度も登場する“地理学”と“お弁当”は、単なる設定や趣味ではありません。
地理学は「人と場所、人と人の関係性」を考える学問であり、まさに物語全体を貫くテーマと重なっています。
主人公の温巳が地理学者として、人との距離や居場所について考え続けていることは、久留里との関係性の変化にも通じているんです。



“地理学”や“お弁当”って、どんな意味を持っていたんですか?



地理学は人との「距離感」、お弁当は「思いやりや絆」を象徴しています。この2つが、血縁を超えた“家族の形”を表すメタファーとなっていました。
そしてお弁当は、日々の思いやりや絆を象徴するものとして描かれています。
特に印象的なのは、温巳が助教試験の提出物として「久留里のために作ったお弁当」を選んだ場面。
このエピソードは、血縁や制度にとらわれない“自分なりの家族”を表現したともいえるでしょう。
作者はこうしたモチーフを通して、「家族とは何か」をやさしく問いかけているように感じられます。
家族と恋愛のあいだにある「曖昧な関係」の意味
『高杉さん家のおべんとう』は、明確な恋愛漫画でもなく、従来の家族ドラマでもありません。
その中間にある「曖昧な関係」を、あえて濁したまま描いているところに、この作品の特徴があります。
久留里と温巳の関係は、血縁がなくても支え合い、信頼し合う“家族のようなもの”として成立していました。
そこに恋愛が加わることで、関係性の境界線が一気にぼやけていく――この“ゆらぎ”こそが物語の本質だったのかもしれません。



家族と恋愛の“曖昧な関係”って、どうしてそこまで重要なんですか?



現代社会では多様な関係性が認められるようになり、“名前のない関係”にも意味があります。この曖昧さこそが、読者への問いかけの本質だったと考えられます。
その曖昧さが読者の共感を生んだ一方で、「結局どういう関係だったの?」というモヤモヤを生んだのも事実です。
現代では、家族の形やパートナーシップが多様化しているからこそ、このような“説明のつかない関係”を描くことに価値がある反面、ストーリーとしては賛否を招く結果にもなりました。
この作品が描こうとしたのは、「名前のつかないつながり」を肯定する優しさ――でも、それがかえって受け手に混乱を残したとも言えるのです。
issyによる『高杉さん家のおべんとう』の深層考察:「気持ち悪い」の正体を読み解く


『高杉さん家のおべんとう』って、一見するとほのぼの系の“家族再生モノ”なんだけどさ、終盤でいきなり「うっ…」って違和感を覚えた読者がめっちゃ多かったんだよな。
理由はズバリ、家族っぽい関係からの「恋愛シフト」って展開。
今回は、その構造がなんで“気持ち悪い”って言われるのか?って話を、明るく丁寧に深掘りしていくぞ〜!
SNSの反応とか、よく比較される『うさぎドロップ』との共通点なんかも絡めながら、「読者のモヤモヤがなんで爆発したのか?」をガチで読み解いていくってワケ!
終盤の“恋愛展開”はなぜ嫌悪感を生んだのか?
まず注目すべきは、やっぱり終盤の恋愛転換。序盤〜中盤までは、年の離れた保護者と少女の“家族的な安心感”が魅力だったんだよね。
でも、ラストに向けて久留里が告白→恋愛関係に…って流れが、「裏切り」みたいに感じた読者がめちゃくちゃ多かった。
特に問題視されたのは、「育ててた相手に恋される」っていう“育成構造”のまま恋愛にシフトしちゃったこと。
これ、SNSでも「うさぎドロップと同じじゃん」ってツッコミが入ってて、「またこのパターンかよ…」っていう“育成→恋愛テンプレ”への拒絶反応が爆発した感じなんだよな。
それに拍車をかけたのが、温巳の「ゴムの心配」のくだり。あれ、「えっ今それ言う!?」って思わずツッコミ入れたくなるレベルで、シリアスを通り越してギャグっぽくなっちゃって、生理的な嫌悪感を強くした読者が多かったっぽい。
つまりこれは、ストーリーの完成度とかじゃなく、“倫理と感情のズレ”が原因で拒否反応を起こしたってワケだ!
フィクションだけど「現実にありそう」なリアルさが逆にキツい!
この作品さ、空気感がめっちゃリアルなんだよ。料理とか日常描写が超ていねいで、「こんな人いそう〜」って共感しちゃう系の作品なんだけど…。
それが逆に、終盤の恋愛展開に現実味を持たせすぎて、「うわ…リアルにこういうのあったらキツい」って生々しさが強調されちゃった感じなんだよな。
『うさぎドロップ』との比較でもよく言われるけど、こっちは“中学生から育ててる”って設定だから、よりリアルなラインに近くて拒否感も強くなるってワケ。
もしもっとファンタジー寄りの作品だったら「まぁフィクションだし」で受け流せたかもしれないのに、日常描写がしっかりしてるぶん「これは無理!」ってなった人が多かったんだよな。
この「リアルなのに共感できない」ってギャップが、“気持ち悪さ”を増幅させたと考えられるね!
作者が描きたかった“曖昧な関係性”がモヤモヤを加速させた
そして、最大のポイントはここ!たぶん作者としては、「恋愛のようで恋愛じゃない」みたいな“関係の曖昧さ”を描こうとしてたと思うんだよな。
作中の地理学ってテーマも、「人と人の距離感」がモチーフになってるし、温巳がずっと“居場所”や“つながり”を考えてるのもその延長線上。
それに、お弁当ってモチーフも「日々の思いやり」や「見えない絆」を象徴してて、かなりメッセージ性のある演出だったわけ。
だけど読者からすると、「家族的な絆」を丁寧に描いてきたのに、最後に急に恋愛に振っちゃうことで「え?結局恋愛に収束するの?」って、テーマ的にもズレを感じた人が多かったんだよね。
現代は“血縁じゃない家族”とか“恋愛じゃないパートナーシップ”とかが普通になってきてるからこそ、この作品の投げかけてた問いはすごく意味があったと思う。
でも、最後の展開が“恋愛関係”に片付けられちゃったことで、テーマの“ぼかし”がうまく機能しなかったって印象なんだよな。
つまり、作者は“名前のない関係”を描こうとしたのに、恋愛というラベルを貼ってしまったことで、モヤモヤだけが残っちゃったってワケ!
結論:違和感の正体は「構造の既視感」と「現実的な重み」
まとめると、『高杉さん家のおべんとう』が“気持ち悪い”って言われる最大の理由は、ただの恋愛描写じゃなくて、「育てた相手と付き合う」っていう構造自体が、既視感アリ+現実的すぎて、めちゃくちゃ重かったからなんだよな。
それが、丁寧に積み上げてきた“家族的な絆”をぶち壊すようなタイミングで入ってきたから、裏切りにも見えちゃったわけ。
しかも、“リアルな描写の良さ”が逆に首を絞める結果になって、「倫理的にもムリ」「感情的にもムリ」っていう二重の拒絶反応を引き起こしたんだと考えられる!
よくある質問
- 高杉さん家のおべんとうはどんなあらすじですか?
-
主人公・高杉温巳(はるみ)は地理学の博士号を取得したものの定職に就けず、中学校の非常勤講師をしながら暮らしています。そんな折、両親を亡くした中学生の姪・久留里を未成年後見人として引き取り、二人で同居生活を始めます。お弁当作りを通じて家族の絆を深めていきますが、物語終盤ではその関係が恋愛へと変化し、賛否両論を呼びました。
- 高杉さんちのお弁当の原作は?
-
原作は柳原望による漫画で、2009年5月号から2015年6月号まで「月刊コミックフラッパー」(メディアファクトリー/現KADOKAWA)で連載されました。単行本は全10巻に加え、後日談を収録した公式ファンブック『高杉さん家のおべんとう メモリアル』も刊行されています。累計発行部数は156万部超 (2024年9月時点)。
- 高杉さん家のおべんとうでくるり役は誰ですか?
-
ドラマ版で久留里(くるり)を演じているのは、女優の平澤 宏々路(ひらさわ こころ)さんです。
- 高杉さん家のおべんとうが「気持ち悪い」と言われるのはなぜですか?
-
序盤は「家族の物語」として描かれていたのに対し、終盤で保護者的立場の大人と未成年の少女が恋愛関係に変わる展開が描かれたためです。家族愛から恋愛への転換に強い拒否感を抱く読者が多く、「気持ち悪い」という批判が広がりました。ただし一方で「成長と自立を描いた物語」と肯定する声もあり、評価は分かれています。
まとめ 作品が残した問いとかすかな余韻
『高杉さん家のおべんとう』は、ほんわかした日常の中に、深くて複雑な問いをそっと忍ばせていた作品です。
「気持ち悪い」と感じた読者がいたのは、単に恋愛描写があるからではなく、家族のような絆が恋愛へと変わる、その過程が持つ“倫理的な境界”に触れてしまったからかもしれません。



結局この作品は、どういう点が読者に強く印象を残したのでしょうか?



恋愛展開そのものではなく、「家族的な関係から恋愛への変化」がもたらす倫理的なゆらぎと、それに対する読者自身の価値観との衝突が強く印象を残した要因です。
SNSやレビューを見てみると、「自分だけじゃなかった」と安心する共感の声もあれば、「これは受け入れられない」と強く否定する声もあって、本当にさまざま。
『うさぎドロップ』と比較されることも多く、育成関係から恋愛に移る構造が、どれだけ多くの人の価値観に影響を与えるかが浮き彫りになりました。
それでも、この作品が最後に投げかけてきた問い――「家族ってなに?」「名前がなくても、大切な関係ってあるよね?」――は、誰もが一度は考えたことのあるテーマだったのではないでしょうか。
登場人物たちの優しさや絆の形は、たとえ賛否があったとしても、多くの読者の心に何かを残したと思います。
もしあなたがこの作品に違和感を覚えたのなら、それはきっと、あなたの中にある価値観や理想が反応した証拠。
次は『うさぎドロップ』など、同じようなテーマを扱った作品と見比べてみると、新しい発見があるかもしれませんよ。


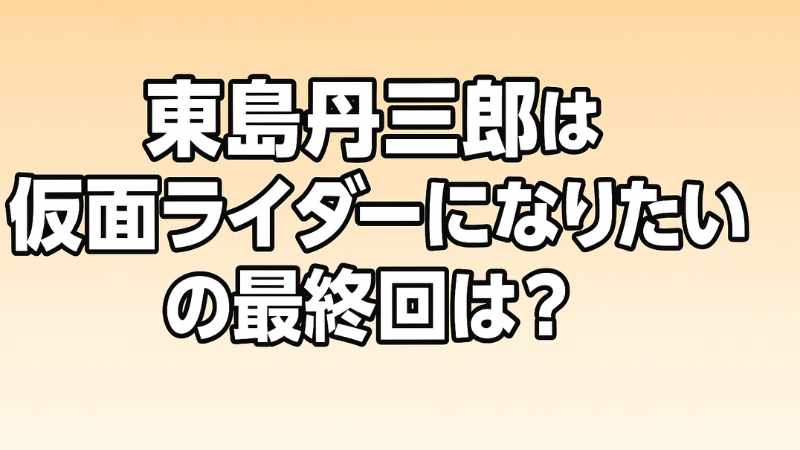
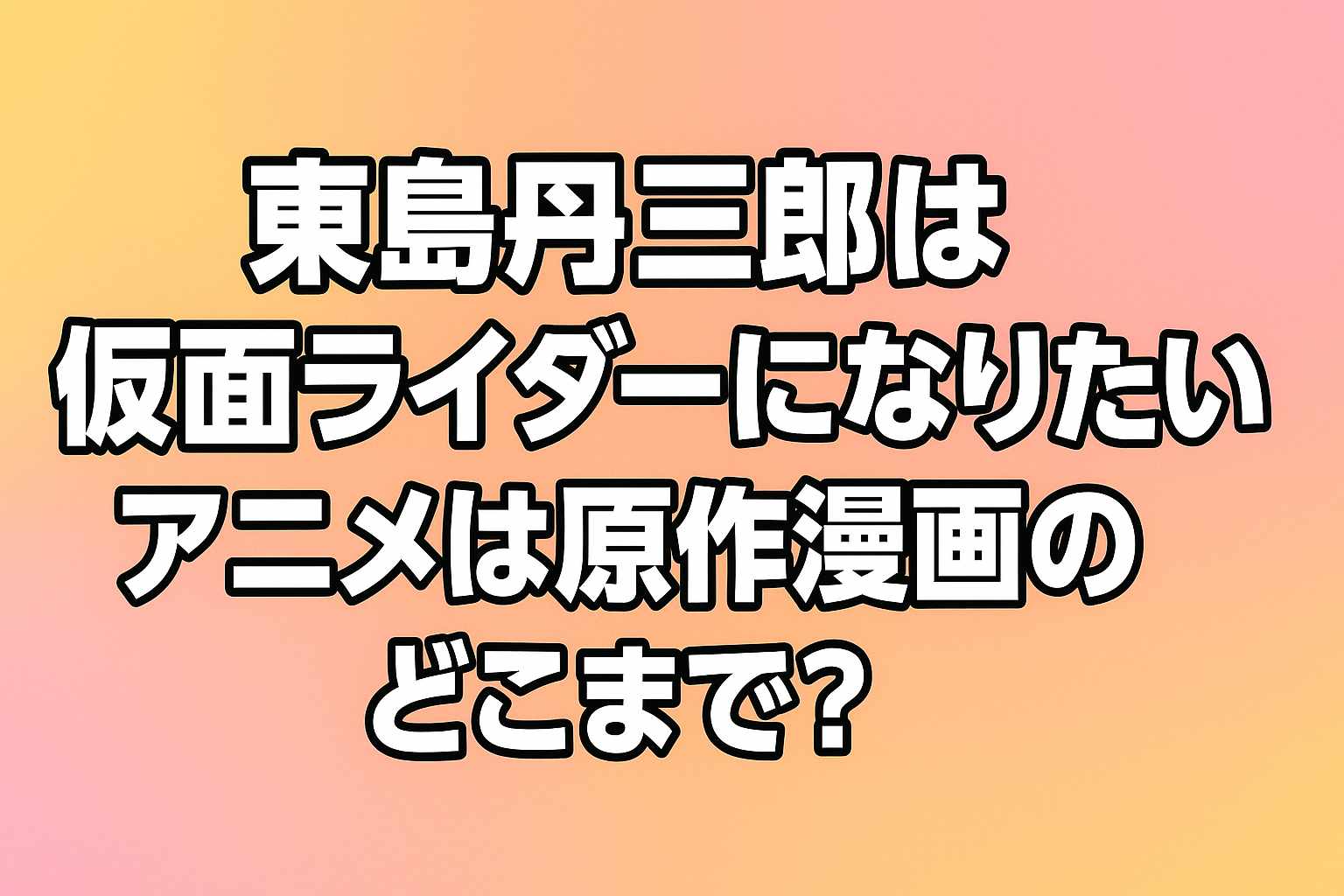
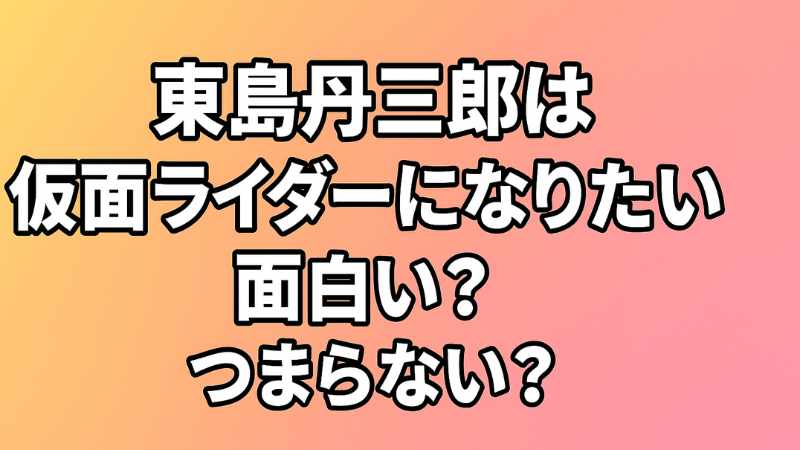
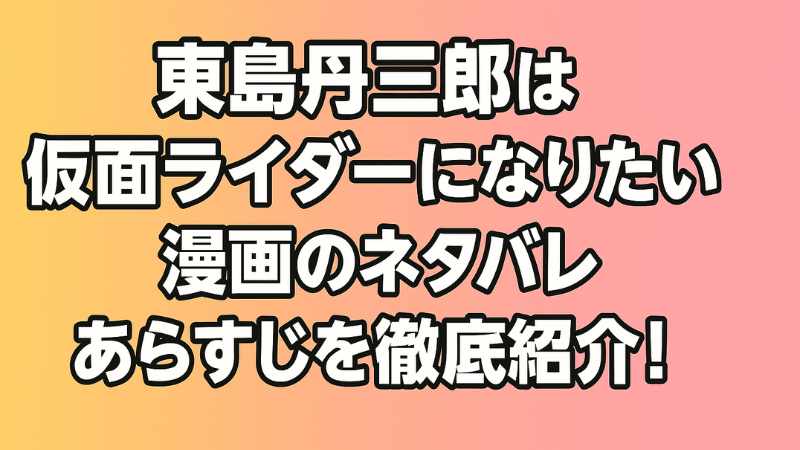

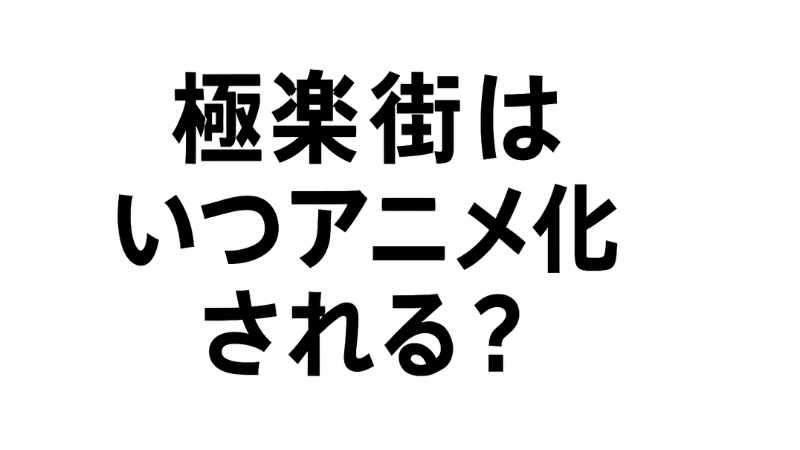
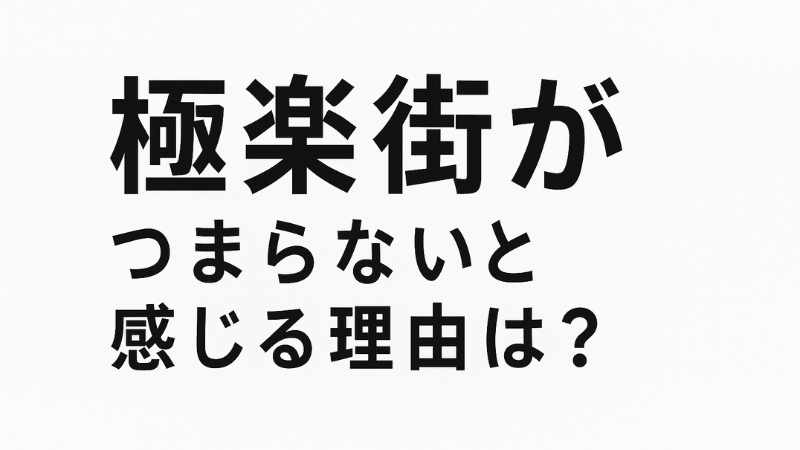

コメント