「IRIS OUT」とは、視界を閉じる演出なのか。
それとも、心の終わりを告げるメッセージなのか。
米津玄師が『チェンソーマン レゼ篇』のために書き下ろしたこの楽曲には、知れば知るほど鳥肌が立つような仕掛けが隠されています。
この記事では、歌詞・映像・原作とのつながりをもとに、その深い意味や背景をわかりやすく、ひとつずつ丁寧に読みといていきます。
この記事を読むと、こんなことがわかります。
- タイトル「IRIS OUT」に込められた意味が見えてきます
- 歌詞の中にある、レゼとの関係や感情が読み取れます
- 予告映像と歌詞のつながりや演出の意図に気づけます
- この楽曲が「ただ悲しい」だけでなく、強い決意も描いていることがわかります
楽曲と物語が重なり合う世界に触れることで、あなたの作品体験はきっと、より深く心に残るものになるでしょう。
本記事は情報量が多いため、気になるところからお読みいただけるよう、目次を設けています。
目次の見出しをタップまたはクリックすると、該当箇所へジャンプします。
『IRIS OUT』は、映画『チェンソーマン レゼ篇』の始まりを告げる疾走感ある一曲ですが、エンディングを彩る『JANE DOE』もまた、物語の深層を描く重要な楽曲です。オープニングとエンディング、対になる2曲をセットで考察することで、作品のテーマがより立体的に浮かび上がります。
→ 米津玄師×宇多田ヒカル「JANE DOE」の意味を徹底考察!歌詞に込めた想いとは?
「IRIS OUT」の意味とは?タイトルが映す終わりのメッセージ

「IRIS OUT」って具体的にどういう意味があるんですか?ただの映画用語ですか?



「IRIS OUT」は映画用語として「画面が円形に閉じて暗転する演出」を指しますが、米津玄師の楽曲ではそれに加え、「視界=感情」「閉じる=終わり」という象徴的な意味が込められています。つまり映像技法以上に、心情や物語の終幕を表すメタファーになっているんです。
『IRIS OUT』というタイトルには、いくつもの意味が込められているようです。
このセクションでは、その象徴性を「映画用語」「生物学的な意味」「物語構造」の3つの視点から深掘りしていきます。
特に『チェンソーマン レゼ篇』との関係性に注目しながら、「視界が閉じる=感情の終焉」というテーマがどのように成立しているのかを整理します。
米津玄師の制作コメントや予告映像とのリンクをもとに、より説得力のある解釈を探っていきましょう。
「IRIS OUT」って何のこと?映像・目・比喩の3つの意味を解説
「IRIS OUT」とは、本来は映画やアニメで使われる映像技法のひとつ。
画面が円形に閉じながら暗転していく演出で、物語の終わりや視点の遮断を象徴しています。
1940-50年代になると「アイリスアウト」の演出自体が様式化されたものとなっていくが、それに伴ってギャグも先鋭化していく。 pic.twitter.com/flLWZ7VhTV
— かねひさ和哉 (@kane_hisa) March 28, 2021
米津玄師がこのタイトルに込めた意味は、それだけにとどまりません。



映像技法だけじゃなく、もっと深い意味があるんですか?



そうなんです。「iris」は英語で「虹彩」、つまり瞳の一部を意味します。光の量を調節し視界の開閉を担う器官で、歌詞に出てくる「瞳孔バチ開いて」ともつながります。さらに「視界が閉じる=恋の終わり」という比喩としても強く作用しているんです。
英語の“iris”は「虹彩」、つまり瞳の一部を指します。
「瞳孔バチ開いて」
(出典:『IRIS OUT』歌:米津玄師/作詞・作曲:米津玄師)
光の量を調節し、視界の開閉を担うこの器官は、歌詞に登場する「瞳孔バチ開いて」というラインともつながってきます。
ここから、「目=感情の通路」と読み解くことも可能なんです。
「視界が閉じる=恋の終わり」といった比喩としても強く機能しています。
「頸動脈からアイラブユーが噴き出て アイリスアウト 」
(出典:『IRIS OUT』歌:米津玄師/作詞・作曲:米津玄師)
「頸動脈からアイラブユーが噴き出て アイリスアウト 」という流れからは、感情がピークに達したその瞬間に視界が閉ざされていく――そんな映像・身体・心情の三層構造が見えてきます。
虹彩=アイリスの比喩とは?視線・恋・終幕をつなぐ隠れた意味
虹彩(アイリス)は、瞳孔の大きさを調整し、光の量をコントロールする器官です。
この「視界のゲート」としての機能が、『IRIS OUT』というタイトルに象徴的な意味を与えています。



虹彩ってただ目の一部なのに、どうして『IRIS OUT』と関係があるんですか?



虹彩は視界の開閉をつかさどる重要な器官で、「見える・見えない」を制御します。そのため楽曲では「視界が閉じる=心の終幕」という象徴に置き換えられているんです。視線の交差や途切れは、恋の終わりや感情の切れ目と直結していると解釈できます。
視線とはつまり、心の接点でもあります。
だからこそ、視線が交わらなくなるとき、そこには“別れ”や“心の終幕”が生まれるんです。
楽曲のなかでは「瞳孔バチ開いて」「アイリスアウト」といった“目”にまつわる言葉が繰り返されていて、感情の高まりと視覚表現が強く結びついています。
このテーマは、『チェンソーマン レゼ篇』のレゼとデンジの関係にも重なります。
ふたりの視線が交差する最後の場面は、まさに恋の終わりを象徴しているように見えるんですね。
こうして「目」というモチーフが、ただの比喩ではなく、物語そのものの核心を描く装置として機能していることがわかります。
米津玄師の制作コメントから読み解く「IRIS OUT」の裏テーマ
『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌『IRIS OUT』は、米津玄師らしい独創的な制作過程から生まれました。
ワールドプレミアのビデオメッセージで米津は、「予告編の出来があまりにも良かった」と語り、映像に使われていた「バン」「ボン」といったSE(効果音)を楽曲に“逆輸入”したと明かしています。
通常は曲に合わせて映像が作られますが、今回はその逆。まさに逆転の発想です。
この制作背景は、「アイリスアウト(IRIS OUT)」という“終わり”を象徴する技法から曲が始まった、という逆説的な構造にも通じます。
楽曲タイトルと予告編の関係が、終わりから始まる物語というメッセージ性を強めているのです。



米津玄師が『IRIS OUT』を作ったとき、どんな意外なエピソードがあったんですか?



ワールドプレミアで米津は「予告編があまりにも良かった」と語り、映像で使われていた「バン」「ボン」といった効果音を楽曲に逆輸入しました。普通は曲に合わせて映像を作りますが、今回は映画が先で曲が後という逆転構造。これは“終わりから始まる”という『IRIS OUT』のテーマとも重なっているんです。
さらに米津は「原作のレゼが映っているページを四六時中睨んでいた」とも語っており、“視る”という行為そのものが創作の軸にあったことがわかります。
これは虹彩=IRISという語とも重なり、視線・執着・終幕というテーマが一つに繋がっていきます。
映像と音、そして視覚への執着。それらがすべて『IRIS OUT』というタイトルに凝縮されているのです。
『IRIS OUT』は、楽曲単体だけでなく映像と合わせて見ることで、レゼ篇との感情的なシンクロがより鮮明になります。
▶︎【公式MV】米津玄師 Kenshi Yonezu – IRIS OUT
歌詞の意味がすごい!「頸動脈からアイラブユー」に隠された本音
ここでは、『IRIS OUT』の中でも特に印象的なフレーズに注目して、それぞれの意味を深掘りしていきます。
「頸動脈」「ざらめ」「アバダケダブラ」「スティグマ」など、ユニークで刺激的な言葉が多く使われており、それぞれに文化的な背景や比喩的な意図があるんです。
これらの語句が『チェンソーマン レゼ篇』のどの場面・心理とリンクしているのかを照らし合わせながら、感情の流れを紐解いていきましょう。



どうしてこんな強烈な単語ばかり歌詞に出てくるんですか?



米津玄師は、甘さだけでなく痛みや暴力性も恋の本質として描き出しています。「頸動脈」「ざらめ」「ゲロ」「スティグマ」などは、それぞれ恋の二面性や危うさを象徴しているんです。だからこそ、単なるラブソングではなく“生々しい恋のリアル”が浮かび上がるわけです。
「頸動脈からアイラブユー」は何を意味してる?愛と死のリアル
頸動脈からアイラブユーが噴き出て
(出典:『IRIS OUT』歌:米津玄師/作詞・作曲:米津玄師)
「頸動脈からアイラブユーが噴き出て」というフレーズは、まさに衝撃的です。
頸動脈は体の中でも最も致命的な部分。
その場所から「アイラブユー」が溢れ出すという描写は、愛そのものが命と直結していることを示しているんですね。
告白する=命を差し出す、というくらいの覚悟が込められているわけです。



頸動脈から愛が噴き出すなんて、すごく危険な表現ですよね?



その通りです。危険だからこそ「愛と死」が重なる表現になっているんです。レゼというキャラクターの「爆弾としての宿命」ともつながり、「好きになった瞬間に終わりが始まる」という構造を強烈に描いています。
この構図は、レゼが持つ「爆弾としての運命」にもつながります。
「好きになった瞬間に終わりが始まる」そんな儚さと暴力性が、この言葉に込められていると考えられます。
『チェンソーマン』では「首」は非常に象徴的なパーツです。
戦闘シーンでは急所として狙われることが多く、レゼも例外ではありません。
デンジと彼女の関係は、親密さと危険が常に紙一重。そうした関係性が、この一行にギュッと凝縮されているようにも感じられます。
このフレーズは曲の後半でも繰り返され、「アイリスアウト=視界の遮断」とセットで使われていることで、愛と死が同時にピークを迎える構造が際立ってくるんです。
「ざらめ」「ゲロ」が意味するもの|甘さと不快の混じる恋心
ざらめが溶けてゲロになりそう
(出典:『IRIS OUT』歌:米津玄師/作詞・作曲:米津玄師)
「ざらめが溶けてゲロになりそう」というフレーズには、恋愛のリアルが詰まっています。
「ざらめ」は、和菓子に使われるような甘くて素朴なイメージ。一方で「ゲロ」は、明らかに不快で生々しい言葉。
その両者を並べることで、「好き」という気持ちの中に潜む甘さと吐き気が同時に表現されているんです。



どうして「ざらめ」と「ゲロ」みたいに真逆の言葉を並べているんですか?



そのギャップこそが恋の二面性を表しているんです。甘いだけの恋ではなく、苦しさや不快さを伴う恋の現実が「ざらめ」と「ゲロ」で同時に描かれているんですね。これはレゼというキャラクターの二面性にも重なります。
これはまさに、レゼというキャラクターの二面性に通じています。
無邪気でかわいらしい一面と、ボムとしての破壊的な本性。
デンジが彼女に惹かれつつも恐れていた、その揺れ動く感情がこの歌詞に反映されているように思えます。
『チェンソーマン』という作品を象徴する“ゲロチュー”のシーンのように、甘さと吐き気が隣り合わせの恋愛観が、デンジとレゼの関係にも通底しています。
この恋がただの理想ではなく、「壊れた美しさ」や「毒を含んだ甘さ」を持っていたことが強く伝わるのです。
米津玄師は、恋愛をただ甘く描くだけでなく、その“汚れ”や“生々しさ”まで表現することで、リアルな恋の苦さと魅力を同時に浮かび上がらせているのです。
「アバダケダブラ」や「スティグマ」って何?元ネタと意味を徹底解説
『IRIS OUT』の中でも、「アバダケダブラ」や「スティグマ」といった言葉は、ひときわ印象に残ります。



この2つの言葉って有名ですけど、歌詞で使われるとどんな意味になるんですか?



「アバダケダブラ」は『ハリー・ポッター』で知られる呪文で、語源的には「消し去る」という意味が含まれています。米津はその破壊性を引用し、恋の“一撃必殺”の危うさを強調しています。一方「スティグマ」は「烙印」「聖痕」を意味し、レゼの起爆印と重なり“逃れられない宿命”を象徴しています。
『ハリー・ポッター』の「アバダケダブラ」は語源に諸説ありますが、本作『IRIS OUT』ではその中でも「消し去る」という破壊的な側面を意図的に取り入れているように読めます。
ラブソングにこの語を配することで、恋が持つ“一撃必殺”の危うさが際立ちます。
「スティグマ」は「烙印」や「汚名」を意味する単語で、宗教的には「聖痕」のニュアンスも持ちます。
額にスティグマ刻まれて
(出典:『IRIS OUT』歌:米津玄師/作詞・作曲:米津玄師)
歌詞では「額にスティグマ刻まれて」とあり、これはレゼの“起爆印”とも重なります。
美しい外見の裏に潜む危険性や、消せない運命を背負うことが表現されているように思えます。
これらの言葉は、決して中二的なワードセンスに終わっていません。
文化的背景と象徴性を持った“比喩の辞書”として機能し、レゼの逃れられなさや、恋愛の運命的な重さを表現する装置となっているんです。
だからこそ聴き手の想像力を刺激し、心に強く残るフレーズになっているのでしょう。
MVと映画でわかる「IRIS OUT」の本当の意味|予告との照合で見えた真実
このセクションでは、映画『チェンソーマン レゼ篇』の本編・予告編・MV、そして米津玄師のワールドプレミアでのビデオメッセージといった一次情報をもとに、「IRIS OUT」の真の意味を探っていきます。
歌詞・効果音・映像構図がどのようにシンクロしているのかを、できるだけ具体的に検証。
ひとつの解釈に決めつけず、複数の視点を提示することで、読者自身が“自分なりの読み”を見つけられるような構成を目指します。



MVや映画の予告と曲がリンクしているって本当なんですか?



はい、本当です。MVや予告で流れる効果音や映像演出が、歌詞やリズムと細かくシンクロしています。これにより、視覚・聴覚・言葉が一体となり「IRIS OUT」のテーマがより鮮明になるんです。
MVと予告がリンク!「ここ弱点」に重なるSEの秘密
MVや予告編で印象的に流れる「バン」「ゾッ」といったSE(効果音)は、楽曲のリズムや歌詞と驚くほど緻密にリンクしています。
矢を刺して ここ弱点
(出典:『IRIS OUT』歌:米津玄師/作詞・作曲:米津玄師)
「矢を刺して」「ここ弱点」といったフレーズに合わせて、映像でも「ズーム」「爆発」「点滅」などの演出が加わり、視覚・聴覚・言葉が一体となった“感情の狙撃”のような演出が完成しているんです。



どうして効果音まで曲に取り込まれたんでしょうか?



米津玄師自身が「予告のSEが良すぎて、音源に取り入れた」と語っています。つまり、映画が先・音楽が後という逆の構造で生まれた作品なんです。この制作順序が「IRIS OUT=終わりから始まる」というテーマと一致しているんです。
注目すべきは、米津玄師が「予告のSEが良すぎて予告編からインスピレーションをいただき、音源に踏襲した」と語っている点。
ふつうは曲が先にあって映像がそれに合わせて作られますが、『IRIS OUT』は逆の構造。つまり「映画が先、音楽が後」という流れで生まれた楽曲なんですよ。
この制作の順序自体が「IRIS OUT=終わりから始める」というテーマと重なっていて、非常に興味深いです。
こうした演出によって、SEは単なる効果音ではなく、「物語の核心を撃ち抜く音」として再定義されているように感じられます。
IRIS OUTの解釈は2つある?“喪失”と“選択”どちらが本当か
「IRIS OUT」という言葉には、たしかに“視界が閉じる”=“終わり”という意味があります。
でもその“終わり”は、ただの喪失だけを指しているのでしょうか?
実は、「意図的に終わらせる」「自分で幕を引く」といった、ポジティブなニュアンスも込められているのではないか、そんな読み方もできるんです。



「終わり」が悲しい意味じゃなくて前向きな選択になることもあるんですか?



そうなんです。『チェンソーマン レゼ篇』のラストで、レゼは逃げずにデンジに会いに行こうとしました。その行動は恋を続けるためではなく、自分の感情に決着をつけるための選択とも解釈できます。つまり“失われる恋”ではなく“終わらせる恋”という能動的なニュアンスがあるんです。
『チェンソーマン レゼ篇』の終盤、レゼが逃げずにデンジに会いに行こうとするシーンがありますよね。
その行動は、恋を続けるためではなく、「自分の感情にけじめをつける」ための選択とも解釈できます。
この“視線の交差”と“すれ違い”の演出が「IRIS OUT」と重なることで、そこにあるのは「失われる恋」ではなく、「終わらせる恋」なのかもしれません。
米津玄師の楽曲やMVの演出も、そうした“意志としての終わり”を丁寧に描いています。
サビで繰り返される「アイリスアウト」は、どこか静かで安らかな響きすら感じられます。
恋に敗れたのではなく、恋を手放すことを選んだ人物の“静かな決意”にも思えるんです。
『IRIS OUT』は、ただの悲恋ではなく、「視界を閉じる」という行為に“意味”と“選択”を与える物語。
その多義的な余白があるからこそ、聴くたびに新しい感情が湧き、何度でも聴き返したくなる魅力があるんですね。
issyによる『チェンソーマン レゼ篇』の深層考察:「IRIS OUT 意味 考察」


『IRIS OUT』ってタイトル、ただの映画用語のオシャレ引用かと思ったら大間違い。
そこには米津玄師が仕込んだ“終わりの物語”の構造がギュッと詰まってるんだよな。
今回はその意味を、映画的な「視界の遮断」って演出からレゼとデンジの関係、さらには「頸動脈からアイラブユー」っていうぶっ飛びワードに至るまで、ガッツリ深掘りしていくぜ!
実はこの曲、「視ること=愛すること=終わらせること」っていう、なかなかエグい構造になってるってワケ。じゃあさっそく、いってみようか!
「視界が閉じる」ってどういうこと?視覚と感情のリンクから見る終わりの演出
「IRIS OUT」って言葉、もともとは映像技法のひとつで、画面が丸く閉じて暗転する演出のこと。でも、米津がそこに込めた意味はそれだけじゃない。
“iris”って英単語には、「虹彩=目の一部」って意味もあるんだ。
「瞳孔バチ開いて」
(出典:『IRIS OUT』歌:米津玄師/作詞・作曲:米津玄師)
で、この曲の歌詞には「瞳孔バチ開いて」とかっていう“目”にまつわる言葉が何度も出てくる。ここから見えてくるのは、「目=感情のゲート」って構造なんだよね。
で、この視覚表現ってのが、ただの比喩じゃなくて、『チェンソーマン レゼ篇』の物語のど真ん中に刺さってるってのがポイント。
デンジとレゼの関係って、最後の最後で“視線の交差”が止まるじゃん。あれこそが「恋の終焉=IRIS OUT」ってワケ!
感情がピークに達したその瞬間、視界がフッと閉じる。
つまりこの曲では、「視界の遮断=感情の終わり」っていうテーマが、映像・身体・心理の三層構造で描かれてるんだと考えられるね。
「頸動脈からアイラブユー」が意味する“命がけの恋”ってなんだよ!?
「頸動脈からアイラブユーが噴き出て」
(出典:『IRIS OUT』歌:米津玄師/作詞・作曲:米津玄師)
さて次は、超インパクトあるライン「頸動脈からアイラブユーが噴き出て」だな。
初見だと「何それ、グロい!?」って思うかもしれないけど、これ、実は超ロマンチックで危うい告白なんだよな。
頸動脈ってさ、言わずと知れた人体の急所。その場所から「アイラブユー」が“噴き出す”ってことは、もう愛=命そのものってレベルの話になってくる。
告白=命を差し出す、みたいな覚悟が込められてるってこと!
しかもこの描写、レゼのキャラ設定とバッチリ重なってる。
彼女って“ボム”として生きてきたから、「好きになった瞬間に終わりが始まる」っていう宿命を背負ってるんだよね。
だから「頸動脈=爆発装置」っていう比喩が、すごくしっくりくる。
このフレーズは曲の後半でも繰り返されてて、「愛が爆発したら視界が閉じる」っていう構造がはっきり見える。
つまり「好き=終わりのトリガー」ってこと。この曲全体が、“命がけの恋”を描いた一大ラブストーリーってわけだね。
“喪失”じゃなくて“決意”?IRIS OUTが描く“終わらせる側”の物語
最後にもうひとつ、注目したいのが「IRIS OUT」って言葉が、ただの“喪失”じゃなくて、“意図的な選択”を意味してるんじゃないかって視点。
つまり、「視界が勝手に閉じた」んじゃなくて、「自分で閉じた」って読み方もできるんだよね。
これ、レゼの行動とめっちゃリンクしてる。ラストで彼女は逃げずにデンジに会いに行こうとする。
でもそれって、「恋を続けるため」じゃなくて、「終わらせるため」だったのかもしれないんだよな。
MVのサビで「アイリスアウト」って静かに繰り返されてるあの感じ、どこか安らかで、暴走の果てじゃなく“決着”の雰囲気すらある。
つまり、「IRIS OUT」は“終わらされる恋”じゃなくて、“自分で終わらせる恋”ってわけ!
この視点で見ると、『IRIS OUT』はただの悲恋じゃなく、「視界を閉じる=自分の意志で幕を引く」っていう、超静かな覚悟の物語に思えてくる。
そこがまた、何回でも聴き返したくなる深さに繋がってるってワケだね。
ってワケで、今回は『IRIS OUT』のタイトルに込められた多層的な意味、「頸動脈からアイラブユー」が描く命がけの恋、そして“終わらせる視線”という選択の物語性まで、一気に掘ってみたぜ!
この考察を書いたのは、アニオタ歴20年以上の陽キャアニメブロガー・issy(いっしー)です。マイナーな名作を見つけて語るのが大好きで、「アニメは人生の教科書」という思いで作品の魅力を発信しています。
よくある質問
- 「IRIS OUT」はいつ発売されますか?
-
2025年9月24日にCDリリースされ、デジタル配信は9月15日からスタートしています。
- 「IRIS OUT」は何の主題歌ですか?
-
映画『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』の主題歌として起用されています。
- 「IRIS OUT」の意味は何ですか?
-
映像技法の一種で、視界が閉じて暗転する演出を意味します。曲では「終わり」や「感情の遮断」の象徴として用いられています。
- 「IRIS OUT」というタイトルにはどんな比喩的意味がありますか?
-
視界の遮断だけでなく、感情や関係性の幕引きを示す比喩が込められている可能性があります。
IRIS OUT歌詞の意味の考察まとめ
この記事では、米津玄師の『IRIS OUT』に込められた象徴的な意味を「IRIS OUT 意味 考察」という視点から解説しました。
- 「IRIS OUT」は視界の遮断を意味する映像技法で、恋の終わりを象徴
- “目”や“視線”が感情と物語の中核を担っている
- 比喩表現として「ざらめ」や「ゲロ」などが恋愛の二面性を表現
- MVや予告編と楽曲がリンクし、視覚・聴覚・心理が連動
- 終わらされる恋ではなく、自ら終わらせる決意を描いている
『IRIS OUT』は“終わり”の中に美しさと選択の意志が宿る作品です。ぜひあなた自身の解釈で、その深い世界観を味わってみてください。



結局、『IRIS OUT』ってどういう作品なんですか?



『IRIS OUT』は単なる映像技法の引用ではなく、「視界の遮断」を恋や感情の終わりに重ね合わせた作品です。さらに“終わらされる恋”ではなく“自ら終わらせる恋”という選択の物語でもあり、聴く人それぞれが新しい解釈を見つけられる奥深い楽曲なんです。


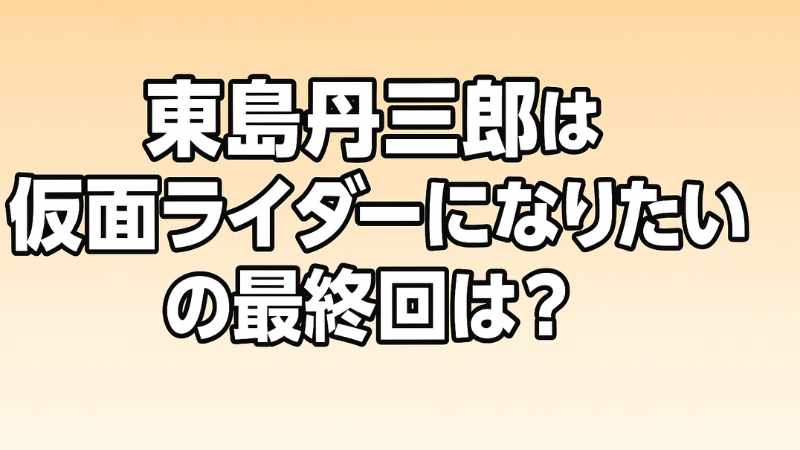
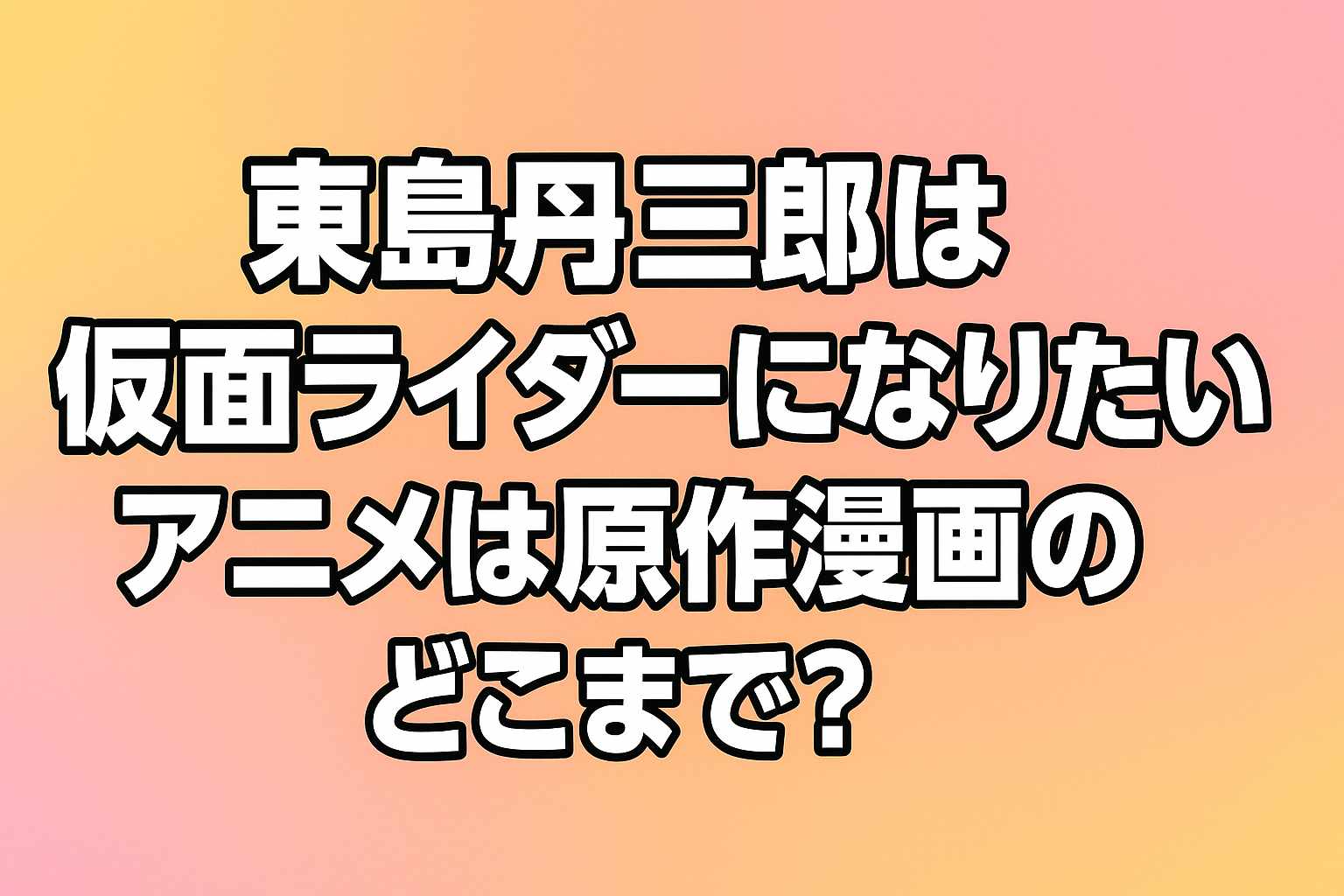
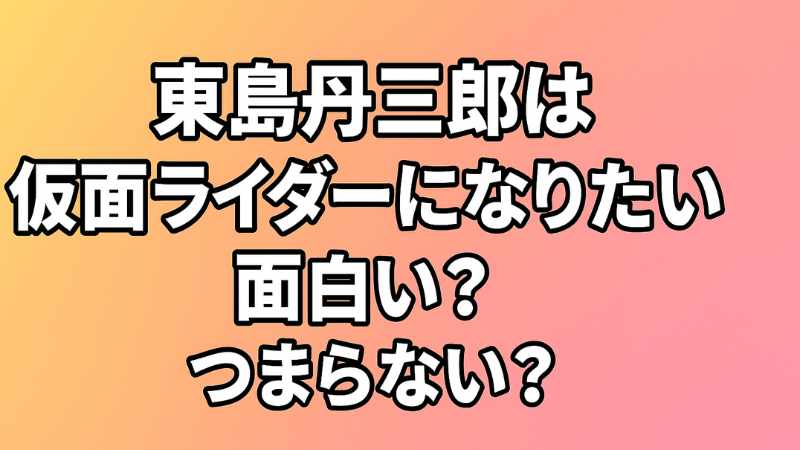
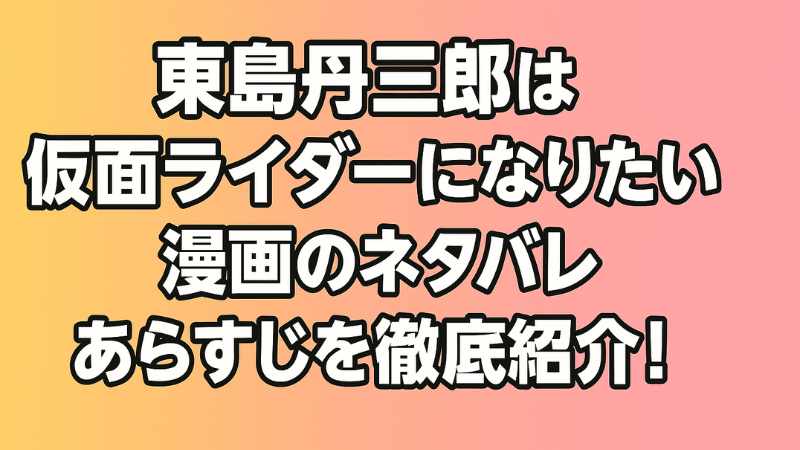

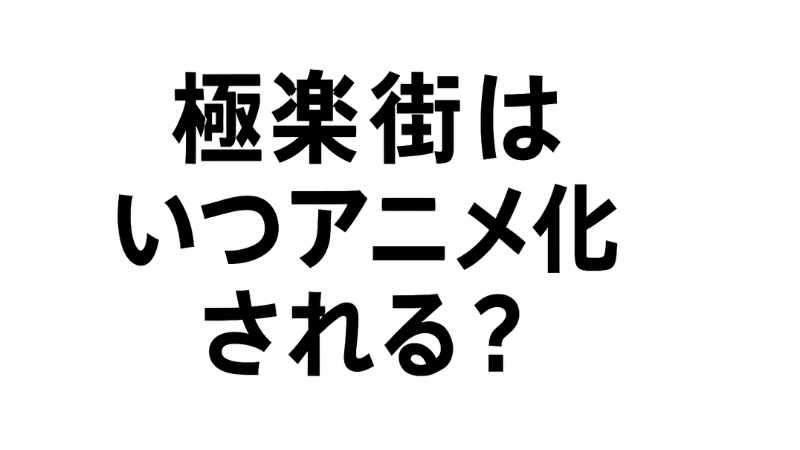
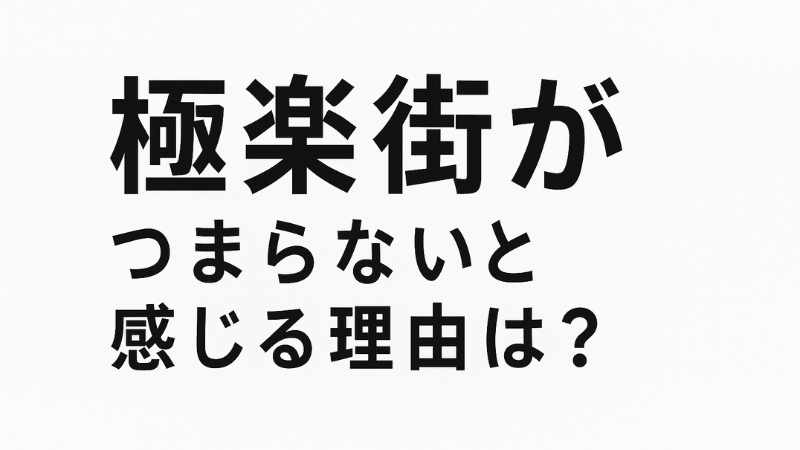

コメント