スタイリッシュで爽快な詐欺アニメ『グレートプリテンダー』。でも「つまらない」という声も?その理由を徹底解説します。
スタイリッシュで痛快、そんな第一印象を持つ人も多い『グレートプリテンダー』。
『コンフィデンスマンJP』の古沢良太氏が脚本を手がけ、WIT STUDIOがアニメーション制作を担当するなど、豪華な制作陣によって生み出された本作は、洗練された映像美とテンポの良い詐欺劇で、放送当時大きな注目を集めました。
その一方で、作品の評価は見る人によって大きく分かれています。
「他に類を見ない独創的なエンターテインメント」と絶賛する声がある一方で、「ご都合主義的で白けた」「主人公に感情移入できない」といった否定的な意見も少なくありません。
詐欺というテーマの扱い方、終盤の大胆な展開、そしてキャラクター設計、こうした要素が、視聴者それぞれの感じ方に大きく影響を与えているのです。
本記事では、「つまらない」と感じた人と、「面白い」と思った人、それぞれの意見をわかりやすく紹介しながら、評価が分かれる理由をシンプルに説明していきます。
この記事を読むと、こんなことがわかります
- なぜ『グレートプリテンダー』が「ご都合主義」「話が浅い」と評されるのか、その背景にある理由
- 主人公エダマメのキャラクター設計が、評価を分ける重要な要因になっている理由
- 「面白い」と感じる人が特に高く評価している要素と視点
- この作品がどんな視聴者に向いていて、どんな人には合わないかを判断するための基準
グレートプリテンダーとはどんな作品?
詐欺をテーマにしたアニメと聞くと、どこか重たく感じるかもしれません。
『グレートプリテンダー』は、驚くほど軽快でスタイリッシュな展開が魅力の作品なんです。世界を舞台に詐欺師たちが繰り広げる“コン・ゲーム”の連続。
その痛快さと映像美は、見る人を一気に引き込みます。まずはこの作品がどんな物語なのか、基本情報をおさらいしておきましょう。

グレートプリテンダーって、どんな作品なんですか?



『グレートプリテンダー』は、詐欺を題材にしつつも軽快でスタイリッシュな展開が魅力の作品です。世界各地を舞台にした“コン・ゲーム”が連続し、映像美と痛快さで視聴者を引き込みます。
詐欺師たちのコン・ゲーム!あらすじと作品概要
『グレートプリテンダー』は、2020年にNetflixで配信されたオリジナルアニメで、全23話を4つのCASE(エピソード)に分けて展開します。
主人公は枝村真人、通称エダマメ。偶然出会った天才詐欺師ローランに引き込まれ、世界中を飛び回る大胆な詐欺計画に加わることになります。
舞台はロサンゼルスやシンガポール、ロンドン、東京と実に多彩で、まるで映画のようなスケール感が特徴。
ジャンルはクライム・エンターテインメント。スリリングな展開とユーモアのバランスが絶妙で、アニメという枠を超えて楽しめる構成になっています。
騙し合いの裏に隠された人間ドラマも、この作品ならではの深みです。



CASEって何ですか?



CASEはエピソードの区切りを意味し、全23話が4つの大きな章に分かれています。そのため、それぞれが映画のような一貫したストーリーを持っているのが特徴です。
2024年の新作『GREAT PRETENDER razbliuto』とは?
前作から時を経て、2024年2月23日にDMM TV独占で配信された待望の続編が『GREAT PRETENDER razbliuto』です。
本作でスポットライトが当たるのは、なんと前作で命を落としたはずの天才詐欺師、ドロシー。
記憶を失った彼女は、台北の街で静かに暮らしていましたが、運命に導かれるように再び裏社会のコン・ゲーム(詐欺計画)に巻き込まれていきます。
彼女の失われた過去には何が隠されているのか。台湾の裏社会を舞台に、新たな仲間と共に繰り広げられるスリリングな騙し合いは必見です。
監督の鏑木ひろ氏と制作のWIT STUDIOが手掛けるスタイリッシュな世界観はそのままに、脚本には新たに岸本卓氏を起用。
従来の軽快さに加え、ドロシーの再生を巡るサスペンスフルな人間ドラマが描かれ、作品に一層の深みを与えています。



ドロシーって、前作では亡くなったんじゃないんですか?



その通りです。『razbliuto』では、死んだはずのドロシーが記憶を失った状態で登場し、そこから新たな物語が展開されます。この意外性が物語の核になっています。
脚本・作画・演出…異色の豪華スタッフ陣
『グレートプリテンダー』の魅力はストーリーだけにとどまりません。
制作陣の顔ぶれも非常に豪華なんです。
脚本を手がけたのは、『コンフィデンスマンJP』などで知られる古沢良太さん。
詐欺をテーマにしながらも、軽快で洒落た会話劇に仕上げる手腕はアニメでも健在です。
アニメーション制作はWIT STUDIOが担当。緻密で洗練されたビジュアルを実現しています。
キャラクターデザインには『新世紀エヴァンゲリオン』で有名な貞本義行さんが参加し、個性豊かで魅力的なキャラを生み出しました。
また、言語演出もユニークで、多言語の会話を日本語の方言(例:東北弁)で表現するという遊び心も光ります。
こうした“映画的”かつ“グローバル”な演出は、日本国内だけでなく海外の視聴者にも強く支持されている理由のひとつといえるでしょう。



制作スタッフって、そんなにすごい人たちが関わってるんですか?



はい、脚本に古沢良太さん、作画に貞本義行さん、制作にはWIT STUDIOといった超一流のスタッフが集まっています。豪華な顔ぶれが、アニメの完成度を高めている要因です。
なぜ「つまらない」と言われるのか?
一見、スタイリッシュでテンポの良い『グレートプリテンダー』。
しかし実際には、「つまらなかった」と感じる視聴者も一定数存在します。
なぜこのような評価が生まれるのでしょうか?
実際の視聴者レビューや意見をもとに、その背景にある理由を掘り下げていきましょう。



見た目は面白そうなのに、つまらないって言う人もいるんですか?



はい、演出やテンポが魅力的な反面、リアリティやキャラ設定に不満を感じた視聴者もいます。好みや価値観によって評価が分かれやすい作品なんです。
詐欺のリアリティが薄い?ご都合主義と感じる理由
本作の詐欺シーンは、見た目には派手でテンポも抜群ですが、「リアリティが足りない」と感じる人も少なくありません。
特に、多人数で押し切る作戦や人情に訴えるオチが多く、詐欺劇としての緊張感や緻密さに欠けるとの指摘が目立ちます。
複数のCASEでトリックの構造が似通っており、「またこのパターンか」と先の展開が読めてしまうという声も。
緻密な頭脳戦やサスペンスを期待していた視聴者にとっては、やや物足りない展開になってしまったようです。
演出や映像美でカバーしてはいるものの、「詐欺」を主題にしているわりに説得力が弱く、スリルに欠ける構造だと感じる人もいるようです。



詐欺ってもっと緻密なイメージなのに、そうでもないんですか?



確かにそのような意見も多いです。『グレートプリテンダー』はエンタメ性を重視しているので、現実的な詐欺の緻密さよりもテンポや演出を優先しています。
主人公エダマメが魅力不足?共感されない理由
物語の中心人物であるエダマメ(枝村真人)には、「魅力が感じられない」という声が多く寄せられています。
特に、「常に他人に振り回され、自分の意志が見えない」「成長の軸が不明瞭で、感情移入しづらい」といった点が評価を分ける要因に。
カリスマ性のあるローランと並ぶと、どうしても存在感が薄く見えてしまい、「物語を引っ張る主人公としては弱い」と感じる人もいます。
エダマメを“未熟な若者像”としてリアルに描いているという見方もありますが、それが視聴者に伝わっていない印象です。
共感を得られない主人公は、物語全体の没入感に大きく影響を与えるため、彼のキャラ設計は賛否の分かれやすいポイントになっています。



主人公なのにあまり人気がないんですか?



エダマメは意図的に“未熟な存在”として描かれているため、そのリアルさが逆に共感しにくいと感じる視聴者もいます。人によって評価が大きく分かれるキャラなんです。
CASE4の賛否が過熱!“全員集合”が蛇足?
シリーズのクライマックスであるCASE4「Wizard of Far East」は、これまでの伏線を回収する集大成の物語です。
その大胆な展開が一部の視聴者にとっては「蛇足ではないか」という疑問を招く要因となりました。
特に指摘されたのが、死んだと思われていた重要人物が“実は生きていた”という結末です。
この大がかりなどんでん返しは、一部で「ご都合主義がすぎる」と受け取られ、物語のリアリティラインを大きく揺るがしました。
最終章のプロットがローランの過去とドロシーを巡る個人的なドラマに強く焦点を当てたため、「コン・ゲームのスリルが薄れてしまった」「これまでの軽快な詐欺劇とは雰囲気が違う」といった違和感につながったようです。
物語の着地点が、一部の視聴者にとって期待していたものとは異なっていたことが、こうした見方を生む背景にあると考えられます。



クライマックスで評価が下がった理由は何ですか?



CASE4では、過去キャラ全員集合や死者の復活など、ご都合主義に感じられる展開が多く、リアリティを求める視聴者から批判が出ました。それが賛否の分かれた原因です。
詐欺というテーマ自体に抵抗感を抱く人も
『グレートプリテンダー』の題材である「詐欺」は、その倫理的な側面から賛否を呼びやすいテーマでもあります。
たとえ相手が悪人であっても、「犯罪行為を娯楽として描くことにモヤモヤする」と感じる視聴者も多く存在します。
キャラクターたちが義賊的に描かれているとはいえ、正義感よりも個人的な事情や感情で動いている場面が多く、善悪の線引きがあいまいなまま進む構成に納得しづらいという声も。
テーマそのものに違和感を抱いたままでは、作品に入り込むのは難しく、評価が分かれる要因のひとつになっているようです。



詐欺ってやっぱりテーマとしては難しいんですか?



そうですね。たとえフィクションであっても、詐欺というテーマに抵抗感を持つ人は少なくありません。特に倫理的に納得しにくいと感じると、作品全体への共感が得にくくなります。
作画や言語演出のクセが合わない人も
視覚的・聴覚的な表現にも独自性の強い『グレートプリテンダー』。その「クセ」が人によってはマイナスに働くこともあります。
たとえば、水彩画調の色彩やビビッドな色使いはアート的で印象的な一方、「見づらい」「目が疲れる」と感じる視聴者も少なくありません。
多言語のローカライズ表現、特に東北弁などを用いた演出は「面白い」と感じる人もいれば、「違和感しかない」と受け入れられない人も。
こうした表現手法は確かに作品の個性ですが、それが合わないと感じた人には、序盤から“しっくりこない”という印象を与えてしまいます。



作画が苦手って人もいるんですか?



はい。水彩調のビジュアルやローカライズの表現が独特なので、芸術的だと感じる人もいれば「見づらい」「違和感がある」と感じる人もいて、好みが分かれる要因となっています。
「面白い」と感じる理由とは?
『グレートプリテンダー』には、「つまらない」という声と同じくらい、「最高に面白かった!」という熱い支持も存在します。
視聴者の心を掴んだポイントはどこにあるのでしょうか?ここでは肯定派の視点から、作品の魅力を紹介します。



やっぱり、面白いっていう声も多いんですね?



はい、多くの人が「どんでん返し」や「スタイリッシュな演出」に惹かれて高評価をしています。作品の魅力を感じるポイントがたくさんあるんです。
爽快などんでん返しと伏線の快感
この作品の醍醐味は、なんといっても「気持ちよく騙される」体験そのものにあります。
各エピソードに散りばめられた伏線が、終盤で一気に繋がり、予想を鮮やかに覆すどんでん返しへと昇華されるのです。
特に、シンガポールの空を舞台にしたCASE2や、ロンドンの美術界を揺るがすCASE3では、その構成の巧みさに「やられた!」と唸る視聴者が続出。
次々と繰り出される驚きの展開は、視聴者を決して飽きさせません。
まるで極上のミステリー映画を観ているかのような爽快感と、パズルのピースがはまる瞬間の快感。
これこそが、『グレートプリテンダー』が多くのファンを惹きつけてやまない最大の理由です。



どんでん返しって、そんなにすごいんですか?



はい、伏線がしっかり張られていて、後半で一気に回収される展開はとてもスリリングで爽快です。観ていて「してやられた!」と感じる瞬間が多いのが特徴です。
“詐欺師”以上の人間ドラマに惹かれる
この物語が観る人の心を掴むのは、詐欺師という派手な仮面の下に隠された、彼らの「素顔」が描かれているからです。
一見、軽薄で自信に満ちた天才詐欺師たち。しかし、その誰もが戦争の記憶、叶わなかった夢、そして愛する人を失った痛みなど、消せない過去を背負っています。
物語は、彼らがなぜ嘘をつき続けるのか、その動機となる人間的な弱さや葛藤を丁寧に解き明かしていきます。
華やかなコン・ゲームの裏で描かれる、切ない過去との対峙。だからこそ、彼らの嘘は時に胸を打ち、仲間との絆はより一層輝いて見えるのです。
ただの痛快な詐欺劇に終わらない、心に深く残る“人間ドラマ”こそが、この作品が持つ最大の魅力と言えるでしょう。



詐欺師の裏側にそんなドラマがあるんですか?



はい、それぞれのキャラにしっかりとした過去や動機があり、人間らしい弱さや葛藤が描かれています。感情移入しやすい構成になっているのも魅力のひとつです。
色彩と音楽が光る!スタイリッシュ演出
『グレートプリテンダー』は、目を引くビジュアルと耳に残る音楽でも高く評価されています。
背景には水彩画のような柔らかなタッチが使われ、極彩色の演出が随所に施されており、まるで1枚のアートを見ているかのような美しさ。
構図も斬新で、画面の隅々まで計算されたデザインになっています。
音楽面でも、ジャズテイストのBGMがテンポ良い物語にぴったりマッチ。
特にエンディングには、フレディ・マーキュリーによる「The Great Pretender」が使用されており、作品の世界観をより魅力的に演出しています。
視覚と聴覚の両面で楽しめるこの作品は、「ただのアニメじゃない」と多くの人に印象づける、芸術性の高い仕上がりになっています。



ビジュアルや音楽も注目ポイントなんですね!



その通りです。色彩の美しさやジャズBGMなど、映像と音の演出が作品の世界観をより深く印象づけています。
セリフとテンポの良さが観やすさを生む
脚本家・古沢良太氏ならではの“言葉の妙”も、この作品の大きな魅力です。
キャラクターたちの会話はテンポが良く、ユーモアと知性がにじむセリフ回しに思わず引き込まれます。
特にエダマメ、ローラン、アビーの3人が繰り広げるやり取りは軽快で、まるで舞台劇を観ているかのようなリズム感。
1話あたり約23分という構成で飽きることなくサクサク観進められるのは、こうした脚本のクオリティがあってこそ。
ストーリーに必要な情報も自然に盛り込まれているため、難しさを感じさせずに理解しやすいのもポイントです。
「わかりやすくてテンポが良い」、その観やすさが多くのファンを惹きつけています。



セリフがうまいと、やっぱり観やすいんですか?



はい、会話のテンポやセンスの良さは作品のテンポ感を支えていて、視聴のストレスを減らしてくれます。飽きずに楽しめる構成です。
評価が真っ二つに分かれる理由
『グレートプリテンダー』は、熱狂的なファンがいる一方で「つまらない」と感じる人も多い、まさに評価が極端に分かれる作品です。
その背景には、視聴者それぞれが作品に求める“価値観の違い”が深く関わっています。ここでは、3つの主な視点からその構造をひもといていきます。



なんでこんなに評価が分かれるんでしょうか?



人によって「リアルさを重視する」か「エンタメ性を楽しむ」かで作品の受け取り方が変わるため、意見が真っ二つに分かれるんです。
リアリティを重視する人 vs エンタメとして楽しむ人
この作品を巡る意見の食い違いの多くは、「リアルさを求めるか、それともエンタメ性を重視するか」という視聴スタイルの違いにあります。
たとえば、緻密な計画や心理戦を期待していた人にとっては、展開の一部が「人情に頼りすぎ」「偶然が都合よすぎる」と映り、説得力に欠けて感じられることも。
一方で、ストーリーのテンポ感や派手な演出、爽快などんでん返しを楽しみたい人にとっては、まさにぴったりの作品です。
どちらの見方も間違いではなく、「何を期待して観るか」によって作品の評価が180度変わるのが、『グレートプリテンダー』の興味深い特徴といえます。



リアルさよりテンポ重視だと楽しめるんですか?



はい、細かいリアリティを気にせずテンポや演出を楽しむ人にはかなり刺さる作品です。エンタメ性を重視する方向けですね。
主人公エダマメの評価が二極化する理由
主人公であるエダマメ(枝村真人)のキャラクターが、作品の評価を分ける大きな要因にもなっています。
「現代的で未熟な青年としてリアルに描かれている」と評価する声がある一方で、「流されるばかりで芯が見えない」「何をしたいのかわからない」と否定的に見る人も少なくありません。
特に、ローランやアビーのような強い個性を持つキャラたちと比べると、エダマメの存在感が薄く感じられてしまうことがあるようです。
この“リアルさ”が逆に“魅力のなさ”として受け取られるケースもあり、同じキャラクターが見る人によって好印象にも不満にも映る――そんな二面性が評価の二極化につながっているのです。



主人公なのに評価が分かれるって珍しいですね。



エダマメの描写はリアルですが、その分、カリスマ性が薄いと感じられることもあり、視聴者によって好みが分かれる要素です。
演出・作画が“クセ強”で好みが分かれる
独特なビジュアル表現や演出も、『グレートプリテンダー』を語るうえで欠かせないポイントです。
水彩画風の色づかいや大胆な構図、多言語を日本語方言で再現するローカライズ手法などは、「センスが良い」と絶賛される一方で、「派手すぎて落ち着かない」「方言がネタっぽくて浮いている」と感じる人も。
これらの個性は作品の大きな魅力であると同時に、視聴者を選ぶ要素でもあります。
「クセが強いからこそハマる人には刺さるけれど、合わない人にはとことん刺さらない」――そんな表現スタイルが、作品への評価をさらに二極化させているといえるでしょう。



方言や色づかいも好みが分かれるんですね?



はい、独自の演出は作品の個性ですが、観る人によって「オシャレ」とも「うるさい」とも受け取られるため、評価が分かれやすいです。
この作品は誰に向いている?
ここまで読んで、「自分には合う作品なのかどうか」が気になってきた方も多いはず。
『グレートプリテンダー』は、はっきりとした個性を持つ作品だからこそ、合う人・合わない人が分かれやすい傾向があります。
ここでは、どんな視聴者に向いているか、逆にどんな人には不向きなのかを整理してみましょう。
グレートプリテンダーが向いている人
テンポの良い展開やスタイリッシュな映像に惹かれる人には、この作品はぴったりです。
巧妙などんでん返しや詐欺劇の構成を楽しめる人、キャラクター同士の掛け合いや心理的な駆け引きにワクワクする人には特におすすめ。
登場人物の過去や内面に触れる“人間ドラマ”が好きな人にもハマりやすいでしょう。
映画のような演出やBGM、鮮やかな色彩といった“映像美そのもの”を楽しむタイプの視聴者にも、強く刺さるはずです。
アニメという枠を超えた作品を探している人にはうってつけです。



『グレートプリテンダー』って、どんな人に向いている作品なんですか?



テンポの良い展開やスタイリッシュな映像を楽しめる方、どんでん返しや心理戦が好きな方に特におすすめです。人間ドラマや映像美を重視する人、アニメを超えた作品性を求める方にもピッタリですよ。
グレートプリテンダーが向いていない人
一方で、リアルで緻密な物語を求める人や、論理的に整合性のある展開を重視する人には、この作品はあまり合わないかもしれません。
詐欺のトリックに“ご都合主義”な側面があるため、説得力を重視する人には引っかかりが残ることも。
また、詐欺というテーマ自体に抵抗を感じる人にとっては、キャラクターに共感しにくくなる可能性があります。
エダマメのような一貫性のないキャラにストレスを感じる人や、落ち着いた色彩・演出を好む人には、演出の派手さが過剰に映るかもしれません。
あらかじめこうした相性を意識しておくことで、作品との向き合い方が変わってくるはずです。



自分が向いているかどうかの判断って難しいですね…



自分が何を求めて観たいのかを意識すると良いですよ。テンポや演出を重視するなら向いていますし、リアリティを求めるなら慎重に判断するのがおすすめです。
issyによる『グレートプリテンダー』の深層考察:「つまらない」と感じる人が続出する“クセ強エンタメ”の宿命


今回取り上げるのは、Netflix発の超スタイリッシュアニメ『グレートプリテンダー』。
めっちゃオシャレでテンポも良いのに、「つまらない」って言う人が意外と多いんよね。
なんでやねん!?ってなるけど、実はそれって、めちゃくちゃ深い理由があるんですわ。いっしーの視点で、ズバズバいくよ!
“リアリティ重視派”がぶつかる、詐欺劇の“ふわっと感”
まず詐欺モノって聞いたら、みんな『ライアーゲーム』とか『カイジ』みたいな、緻密でヒリつく心理戦を期待するやん?
でも『グレプリ』は全然違う。コン・ゲームっていうジャンルを、スタイリッシュにテンポよく、気持ちよ〜く“魅せる”のが目的なのよ。
だからリアルな詐欺の手口より、「騙された!」って爽快感の方が優先されてる。
ここがミソ。でもね、そこに違和感覚える人も出てくるわけ。
「またこのパターンか…」とか「人情で解決しすぎじゃね?」って思う人には、詐欺劇としての緊張感が物足りなく感じちゃうんよな。
でもそれも含めて、エンタメとしての方向性。
ノリ重視、テンポ重視。それが『グレプリ』の流儀なんやけど、そこに乗れなかった人からすると「詐欺ってよりごっこ遊びでは…?」ってなるのも、まぁわかる話ではある。
主人公エダマメ、“感情移入できるか”が評価の分かれ道!
続いてエダマメ問題。記事でもズバッと書かれてたけど、「主人公として地味すぎん?」とか「芯がないよね」って声、結構多い。
でもこれ、いっしー的にはあえて狙ってやってると思うのよ。
ローランやアビーはもう、バチバチにカリスマあるじゃん?でもエダマメは、迷う、振り回される、ブレる。
詐欺師として未完成で、普通の人感が強い。だからこそ、視聴者が「わかるわ〜その気持ち…」って感情移入しやすい設計になってると思うんよ。
けど逆に言うと、「しっかり引っ張ってくれる主人公が観たい!」って人には、ちょっと頼りなく見えちゃう。
リアルな人間っぽさか、魅力のなさか――この受け取り方の違いが、作品全体の評価をガラッと変える分岐点になってるのは間違いない!
色彩・演出・言語──“センス爆発”が逆にアダに?
そして演出まわりも見逃せない。
『グレプリ』って、見た目も音もバッチバチに決まってるやん?水彩調の背景にビビッドな色彩、構図もおしゃれ、音楽はジャズ、EDはフレディ・マーキュリー。
…いや、どんだけ攻めるん!?って感じ
でもね、これが刺さらない人にはまったく刺さらんのよ。
「色がキツくて疲れる」「多言語を東北弁で表現されると混乱する」って声もあるある。
センス全振りだからこそ、視覚や聴覚への情報量が多くて、疲れる人も出てくる。
言い換えれば、“わかる人にだけわかってもらえればOK”っていう割り切った作り。
だから、ハマる人にはドハマり。でも合わない人には「最初から最後までしんどかった…」ってなる。これぞ“クセ強エンタメ”の宿命やね!
どう?ここまで読んでみて、「あ〜確かに!」って思った人も、「いややっぱ詐欺は論理でしょ!」って思った人もいると思うけど、それこそがこの作品の面白いところなんよな〜。
よくある質問
- 『グレートプリテンダー』と『コンフィデンスマンJP』はどちらが先ですか?
-
放送開始は『コンフィデンスマンJP』(2018年)が先ですが、『グレートプリテンダー』は2012年から企画が進行していたとされています。どちらも脚本家・古沢良太氏による作品で、詐欺をテーマにしつつ、それぞれアニメと実写という異なるメディアで展開されました。
- プリテンダーとコンフィデンスマンの違いは何ですか?
-
『グレートプリテンダー』はアニメで、国際色豊かな詐欺劇を描くシリアス寄りの作品です。一方『コンフィデンスマンJP』は実写ドラマで、コメディ要素が強く、映画では海外を舞台にしたエンタメ性が際立ちます。
- 『GREAT PRETENDER』はどんな話ですか?
-
詐欺師たちが世界を舞台に悪人をだます、爽快感と人間ドラマが交差するアニメです。各エピソードごとに物語が分かれており、最終章でキャラクターたちの背景が交錯する構成になっています。
- 『グレートプリテンダー』の続編はいつ?どこで見られるの?
-
2024年2月23日に、『GREAT PRETENDER razbliuto(ラズブリウト)』がDMM TVで独占配信されました。ローランの過去と彼に深く関わった女性ドロシーの新章で、実質的にシリーズの続編(第3期)として位置づけられています。
まとめ:評価が割れるからこそ、観る価値がある
『グレートプリテンダー』は、「つまらない」と「面白い」が真っ向からぶつかり合う、めずらしいタイプのアニメです。
色彩豊かな映像、巧妙などんでん返し、そして詐欺というユニークなテーマ。
そのすべてが作品の“面白さ”につながる一方で、リアリティや共感性の不足と受け取る人もいます。
こうした評価の振れ幅が大きいからこそ、一度は観てみる価値があるのです。最後に、視聴を迷っている人の判断材料となる2つの視点をご紹介します。
“つまらない”も“面白い”も成立する構造
この作品がここまで評価を分けているのは、「視聴者のスタンスによって見え方がガラリと変わる」という独自の構造にあります。
テンポの良さやスタイリッシュな演出を楽しむ人にとっては、まさに爽快な傑作。
リアルさや倫理的な整合性を重視する人には、薄っぺらく感じられる部分もあるでしょう。
どちらの意見も否定されるべきではなく、それぞれが正当な“受け止め方”なのです。
だからこそ、『グレートプリテンダー』は賛否がありながらも語られ続ける、特別な存在になっているのです。
判断基準は「自分に合うかどうか」
最終的に大事なのは、「自分に合う作品かどうか」を見極めること。
詐欺や騙し合いをエンタメとして楽しめるかどうか、主人公の成長よりもチームの駆け引きを重視するタイプか、刺激的なビジュアルを求めるか。
そんな自分の“好き”をもとに、作品との相性を判断するのが一番です。
他人の評価に流されるのではなく、この記事のポイントを参考にして、自分の価値観と照らし合わせてみてください。
「思ったより面白かった」「やっぱり合わなかった」——どちらでも間違いではありません。
大切なのは、自分の目で選んで納得すること。その視点を持って、ぜひ『グレートプリテンダー』をチェックしてみてください。



最後に一言、観るか迷ってる人にアドバイスはありますか?



評価が分かれる作品だからこそ、自分の目で観て判断する価値があります。スタイルやテンポが合えば、きっと印象に残る作品になるはずです!

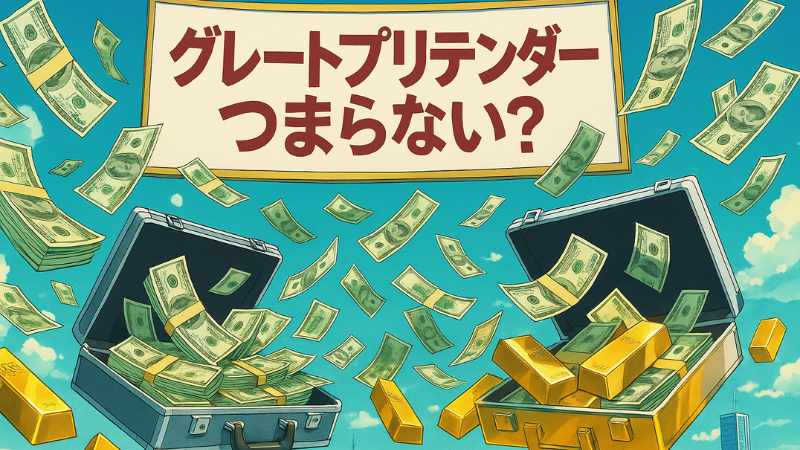
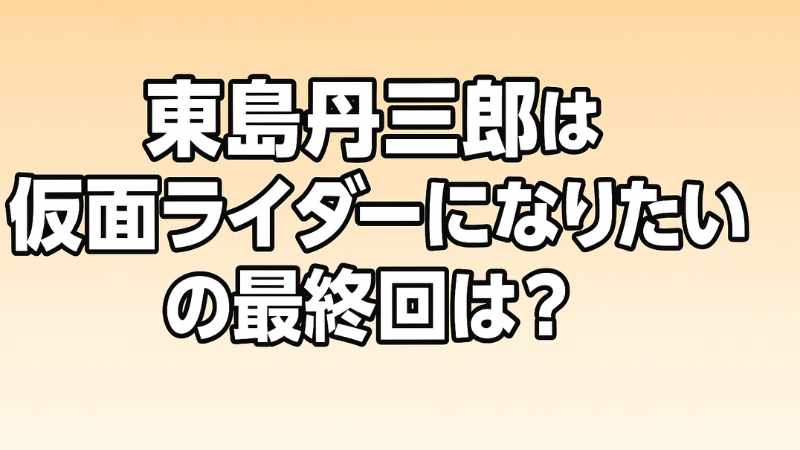
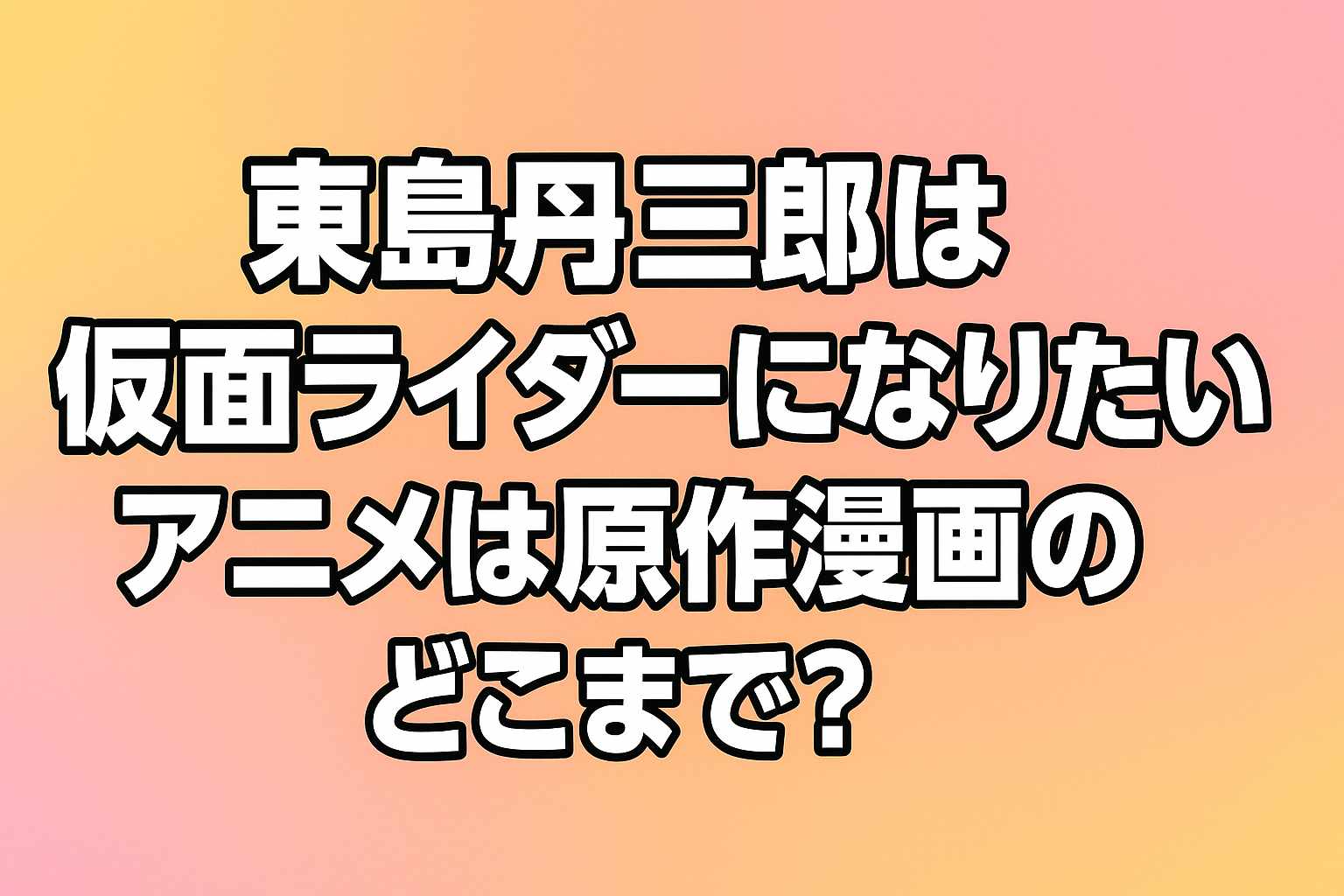
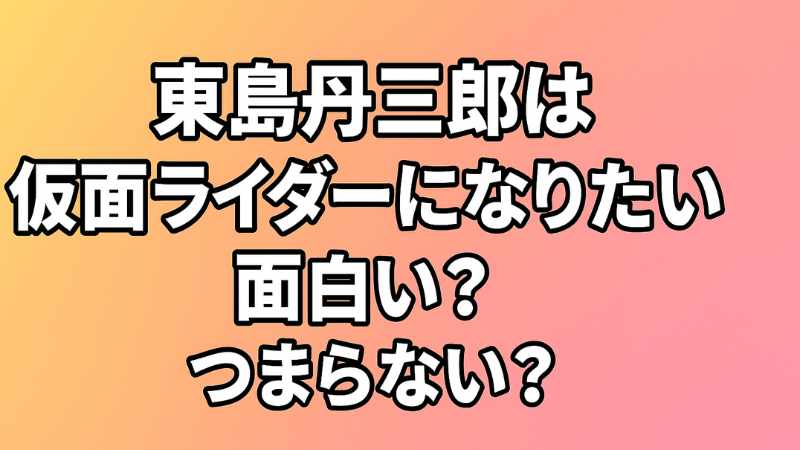
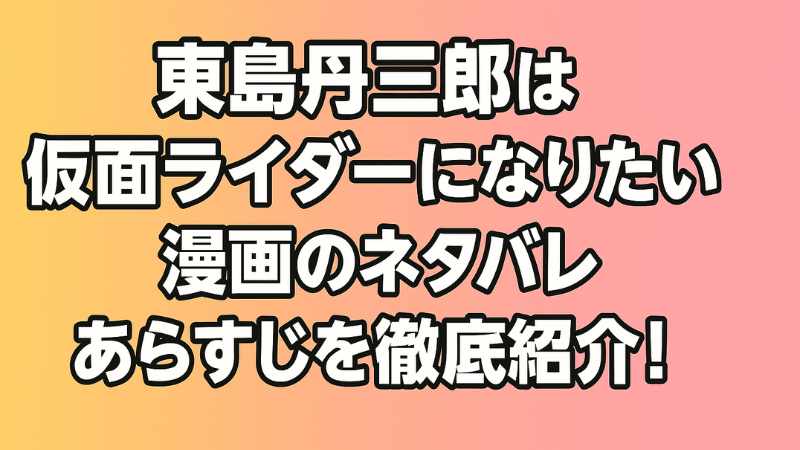

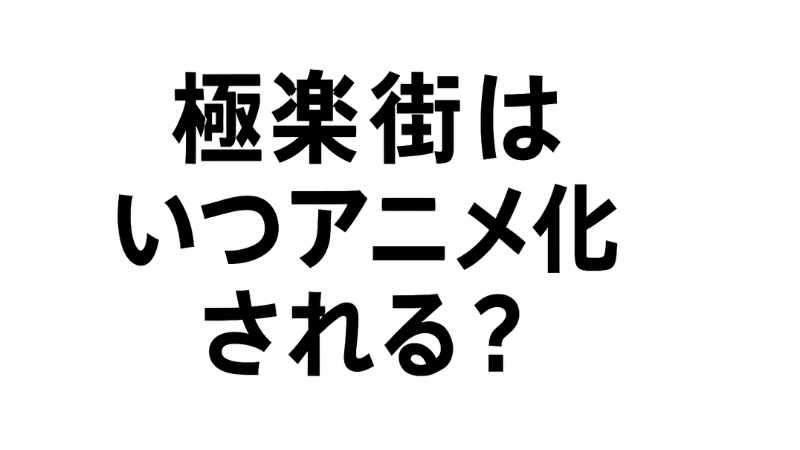
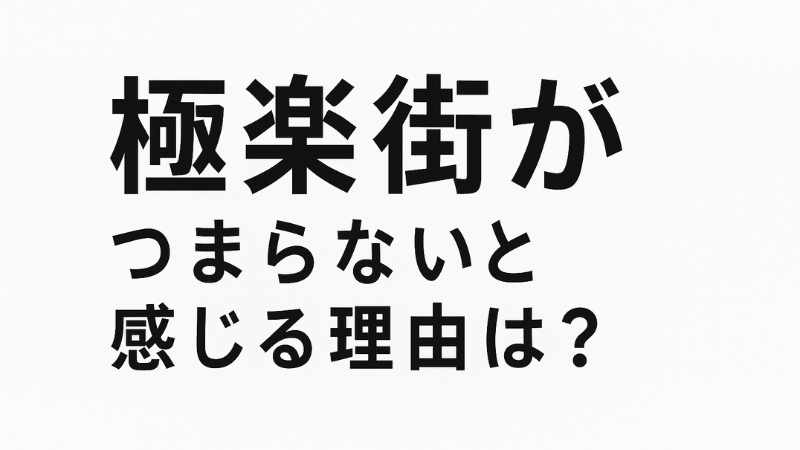

コメント