「ブルーピリオドが気持ち悪い」と言われる5つの理由を徹底解説。心理描写や媒体ごとの違和感を整理し、自分に合った楽しみ方を見つけるヒントを紹介!
登場人物の心理描写や作品のトーンに「気持ち悪い」と感じる――そんな声が『ブルーピリオド』に多く寄せられています。
リアルな成長物語として高い評価も受けており、そのギャップに戸惑う読者も少なくありません。
『ブルーピリオド』が気持ち悪いと言われる5つの主な理由を、原作・アニメ・実写の媒体別にわかりやすく整理。あなたの違和感の正体を一緒に見つけていきます。
この記事を読むと
- 『ブルーピリオド』に対する「気持ち悪さ」の具体的な要因がわかる
- 原作・アニメ・実写それぞれで違和感が生じやすいポイントを理解できる
- 違和感の背景にある心理メカニズムを知ることができる
この記事を読むことで、作品をどう受け止めればよいかがクリアになります。
ブルーピリオドが気持ち悪いと感じられる主な5つの理由
「ブルーピリオドが気持ち悪い」と感じた人、それ、あなただけではありません。
実はこの“違和感”には、共通するポイントがあるんです。
この記事ではまず、どんな読者がどんなシーンで「キツい」と感じやすいのかを整理。
あわせて、自分がどのタイプの読者かをチェックできるヒントもお伝えします。

ブルーピリオドを読んで「気持ち悪い」と感じるのは、私だけでしょうか?



いえ、そのように感じる方は意外と多いです。特に心理描写の生々しさや、キャラクターの極端な表現が読者の感受性に強く影響を与えているためです。本文ではその主な理由を分かりやすく解説しています。
気持ち悪いと評される主因まとめ
「ブルーピリオドが気持ち悪い」と言われる主な理由は、次の五つに集約されます。
生々しい心理描写
→ 主人公・八虎の内省がリアルすぎて、読む側が“しんどく”なる(共感性羞恥が発生しやすい)。
→ 例:合格発表前夜の自問自答シーン。
価値観ギャップ(才能 vs 努力)
→ 「才能の開花」が急すぎて、ご都合感やチート感に違和感。
→ 特に「高3から藝大合格」は現実離れして見える人も。
演出の過剰・尺の偏り
→ アニメでは内面のセリフが音や映像で増幅され、圧が強く感じられることも。
→ 一方で「肝心な関係性が雑に流れる」といった編集の偏りも。
キャラの作劇的描写
→ 脇役の性格や行動が極端すぎて、不快感を覚えることも(特に龍二や世田介)。
→ リアリティより“演出感”が勝って見える。
実写の駆け足化
→ 限られた尺に詰め込みすぎて、人物が薄く心情が伝わりにくい。
→ 原作既読者ほど違和感が強くなりがち。
どれかひとつでも「わかるかも」と思った人は、この記事後半で紹介する“自分の違和感タイプ”や、それに合った媒体(原作・アニメ・実写)をチェックしてみてください。



たしかに共感性羞恥ってありますね…。そう感じる人は多いのでしょうか?



はい、心理描写に敏感な読者ほど「自分ごと」のように感じてしまう傾向があります。ブルーピリオドではそれが顕著に表れており、心の奥にある未整理の感情が刺激されやすくなっています。
肯定派の視点とバランス
「ブルーピリオド」を“気持ち悪い”と感じる声がある一方で、熱心に支持する読者も少なくありません。彼らが評価するポイントは、大きく三つあります。
ひとつ目は、リアルな受験描写です。藝大を目指す過程でのプレッシャーや模試の結果に一喜一憂する様子は、受験経験者には胸が痛くなるほどリアルなんですね。
SNSでも「予備校あるあるすぎて泣ける」という声が多く見られます。
次に挙げられるのが、作者・山口つばさ氏の藝大経験に基づく描写の信頼感です。
デッサンの評価基準や講評シーンの細かさは、実体験に裏付けされた“現場の空気”が感じられ、美大関係者からの共感も得ています。
「ここまで踏み込んだ漫画はなかった」というレビューもあるほどです。
そして三つ目が、成長物語としての魅力です。八虎が絵と向き合いながら自己を見つめ、仲間と衝突しながらも成長していく姿に、「自分も頑張ろうと思えた」と励まされる読者も多いんです。
肯定派にとって“気持ち悪さ”すら、「リアルさ」や「心の成長痛」として受け入れられる要素になっています。
このように、否定的な印象と紙一重のリアリティがあるからこそ、「刺さる人には深く刺さる」作品になっているんですね。



逆にブルーピリオドを肯定的に見る人は、どんなところを評価しているのですか?



肯定派は「リアルな受験描写」「作者の体験に基づいたリアリティ」「成長物語としての魅力」などを高く評価しています。特に自身が美大受験などの経験者であると、共感がより強くなるようです。
媒体別×論点:原作・アニメ・実写の違いを一目で理解する
「ブルーピリオド」の印象は、どの媒体で体験するかによって大きく変わります。
「原作は重たいけど好き」「アニメはテンポが速すぎた」「実写はなんか違う」……そんな感想を聞いたことはありませんか?
このセクションでは、原作・アニメ・実写それぞれの特徴と、どんな違和感が出やすいかを整理して、自分に合った入り口を見つけるヒントをお届けします。



ブルーピリオドって、どの媒体で見るかで印象が変わるんですか?



はい、それぞれ異なる演出や表現方法があるため、作品の受け取り方が大きく変わることがあります。自分に合った媒体を選ぶことが、より深く作品を楽しむコツですよ。
原作で気持ち悪さが出るポイント



原作って、どんなところが“しんどい”と感じやすいんでしょうか?



原作は心理描写が非常に濃密で、特に八虎の葛藤や内省がリアルすぎると感じる人が多いです。感受性が強い読者ほど、感情が引っ張られてしんどくなる傾向があります。
原作漫画「ブルーピリオド」は、特に内面描写の濃さが読者の好みを分ける要素になっています。
コマ割りが密でセリフ量も多いため、八虎の内省が長く続くと「読むのがしんどい」と感じることもあるんです。
八虎が初めて絵に目覚めたあとに自己否定に陥る場面。「何のために描くのか?」「才能って何?」という問いを繰り返す描写は、読者の過去の経験や悩みと重なって、感情の投影や共感性羞恥が引き起こされやすくなります。
予備校での厳しい叱責や講評の言葉も、現実に近いからこそ心に刺さる場面が多いんですね。
大学編に入ると、群像劇の要素が強まり、視点が散漫になったように感じる読者もいます。
これは作者が藝大の多様性を描こうとした結果ではありますが、「誰に感情移入すればいいのか分かりにくい」という声も見られます。
「漫画は好きだけど読後感が重い」と感じたなら、巻を分けて読む、主要なセリフだけを追って読むといった工夫が効果的です。
アニメで気持ち悪さが出るポイント



アニメだと“圧が強い”って聞いたんですが、それってどういう意味ですか?



色彩や演出が強調されていて、感情が視覚・聴覚に強く訴えかける構成なんです。特に八虎のモノローグ場面は共感性羞恥を感じやすく、観る人によっては“しんどさ”につながります。
アニメ版「ブルーピリオド」は、映像と演出の強さが特徴です。
そのぶん、“圧”を感じやすく、「観ていてしんどい」となる場面も増えています。
特に八虎の内面モノローグが流れる場面では、背景の色彩が激しく変化し、表情のアップが繰り返されます。
これは“恥ずかしい気持ち”を視覚的に強調するため、共感性羞恥を引き起こしやすくなっているんです。
1クール(全12話)で大学受験までを描くため展開が早く、心理描写の積み上げがやや不足している印象も。
とくに「もう合格?早すぎない?」といった声は多く、アニメ化に伴う制約が影響しているともいえます。
アニメならではの魅力もあります。
原作では静止画だった絵が動きや音とともに表現されることで、“描くこと”の熱量がダイレクトに伝わるのです。
筆の動きや絵の具のにじみ、息遣いの効果音などは、視覚と聴覚に訴えかけてきます。
「ちょっとしんどいかも」と思ったら、音量を下げたり、1話ずつ間を空けて観たりすることで、気持ちの余裕を保ちながら楽しめますよ。
実写で気持ち悪さが出るポイント



実写版って「違和感が強い」と言われるのはなぜなんですか?



尺の短さによる展開の粗さや、キャスティングの印象が原作と違うことが主な理由です。特に原作ファンには物足りなさやズレを感じやすい構成になっています。
実写版「ブルーピリオド」は、原作の数巻分を約2時間の映画に凝縮しており、その駆け足感や演出の粗さがどうしても目立ってしまいます。
これが“気持ち悪い”と感じられる主な理由の一つです。
まず大きいのが、時間的制約による感情描写の薄さです。
八虎の葛藤や変化がわずかなセリフや回想に集約されており、観る側が感情的に追いつけないんですね。
美術への目覚めや藝大合格までの道のりがあっさり描かれていて、「感動の積み上げがない」と感じる声が多くあります。
次に、キャスティングに違和感を覚えるという意見も少なくありません。
八虎の表情やテンションが「原作より明るく軽く見える」といった反応が目立ち、作品世界に入り込みづらくなっているんです。
原作で抱いていたキャラ像とのズレが、視聴者の没入を妨げる要因になっています。
八虎と龍二、佐伯先生との関係性など、物語の中核となる人間関係が十分に描かれないまま進行するため、「このキャラ誰?」「関係性が薄すぎて感情移入できない」といった印象も。
限られた尺のなかでは仕方ない部分ですが、原作を知っている人ほど物足りなさを感じやすいようです。
そのため、実写版は「ブルーピリオド」の入門としてではなく、原作を読んだあとに“別視点での再解釈”として楽しむのが向いているかもしれません。
人物・場面別検証:どのキャラ・場面が違和感の引き金か
「ブルーピリオド」を読んでいて「なんとなく共感できない」「どこか引っかかる」と感じる場面。
その多くは、特定の人物の言動やシーンがきっかけになっています。
このセクションでは、主人公・八虎をはじめ、個性的な脇役たちが生む違和感ポイントを、具体的なシーンと一緒に掘り下げていきます。



登場人物によって違和感の強さが変わるんですか?



はい、特に八虎や脇役たちの描写は極端な感情表現を含むため、人によって共感できる・できないが分かれやすいです。心理的な負荷を感じる読者も少なくありません。
矢口八虎の違和感ポイント



八虎って共感できるようでできない、不思議な主人公ですよね?



まさにその通りです。感情の揺れ動きや自己否定がリアルすぎて、読者自身の内面を刺激してくるタイプのキャラです。「苦手」と感じる人が出やすいのもそのせいです。
矢口八虎は、“自分を偽って生きていた高校生がアートに目覚める”という、非常にドラマチックなキャラクターです。
その急激な変化や内面の描写が「リアルすぎて苦手」「感情についていけない」と感じさせることもあるんです。
最初に挙げられるのが、見た目と実力のギャップです。チャラくて不真面目に見える八虎が、突然藝大を目指す展開に「説得力がない」と違和感を覚える読者もいます。
美術を始めてからの上達スピードがあまりに早く、「結局は才能頼り」と見えてしまう場面も。
自己否定の激しさも評価が分かれるポイントです。
たとえば、試験前に「自分には描く資格がない」と泣き崩れる場面。
感情移入できる人には強く響く一方で、「また同じような悩み?」「重すぎる」と感じてしまう人も少なくありません。
作中では飲酒や喫煙の描写もあり、「高校生なのに?」という現実とのギャップに引っかかるという声もあります。
このような“リアルさ”が逆効果となり、読者に心理的な距離を生んでしまうんですね。
八虎を「作者自身の分身」と考えてみると見方が変わってきます。
実際の藝大受験を元にした“私小説的な成長物語”として読むことで、彼の葛藤や迷いがよりリアルに、そして納得感を持って理解できるかもしれません。
脇役の受け取り方差



脇役たちにも違和感を感じるんですが、そういう声って多いですか?



多いです。特に龍二や世田介のように強い個性や重いテーマを背負ったキャラは、共感される一方で「理解しにくい」「感情的にしんどい」と感じる読者もいます。
「ブルーピリオド」では、八虎だけでなく、脇役たちも物語を大きく動かしています。
ですが、その個性の強さが「受け入れにくい」「気持ち悪い」といった反応につながることもあるんです。
たとえば、龍二(りゅうじ)。男性として育てられながら女性の服を好み、ジェンダーに悩む姿は深く描かれています。
芸術を通じて自分を表現しようとする姿勢には共感が集まる一方、「性の描写が生々しい」「思考が重たすぎる」といった受け止め方もあり、読者によって賛否が大きく分かれる存在です。
特に「家族や社会の抑圧」と「自己否定」が交錯する場面では、過去の経験を刺激されてつらく感じる人も。
次に世田介。孤高の天才タイプで、人との距離感が極端に遠く、発言も冷たい印象を与えます。
「リアルだけど不快」「言い方がキツすぎる」と感じる人も多く、とくに予備校の講評シーンでは「他人を傷つけてまで言う必要ある?」という反応が目立ちました。
佐伯先生は八虎を藝大へ導く重要な存在ですが、その厳しさと感情を表に出さない姿勢が「冷たい」「怖い」と受け取られることもあります。
言葉は的確でも、感情の交流が見えづらいため、読者との距離を感じさせるんです。
脇役たちの個性は作品に深みや多様性をもたらしていますが、同時に“主人公に感情移入したい”タイプの読者にとっては、焦点がぼやける原因にもなります。
「なぜこの人の話をこんなに掘り下げるの?」と感じる瞬間が、作品との距離を生む要因にもなり得るのです。
心理メカニズム:なぜ人は「気持ち悪い」と感じるのか
「ブルーピリオド」が“気持ち悪い”と感じられるのは、単にストーリーやキャラ設定のせいではありません。
その背景には、人間の心理的な仕組みが大きく関わっています。
このセクションでは、「共感性羞恥」や「投影」「価値観のギャップ」といった心理キーワードを使って、なぜこの作品に“しんどさ”や“不快感”を覚えるのかをひも解いていきます。



気持ち悪く感じるのって、心理的な理由があるんですか?



はい、非常に深い心理的反応が関係しています。共感性羞恥や投影など、自分自身の過去や感情が刺激されることで“気持ち悪い”という感覚になることが多いです。
共感性羞恥と投影の仕組み



共感性羞恥って、どんな感覚なんでしょう?



誰かが失敗したり恥ずかしいことをしているのを見て、自分まで恥ずかしくなってしまう感覚です。八虎のようなキャラが自分をさらけ出すと、読者も心が痛くなるんですね。
「共感性羞恥」という言葉を聞いたことがありますか?
これは、他人の失敗や恥ずかしい言動を見て、自分まで居たたまれなくなる感覚のことを指します。
「ブルーピリオド」では、八虎が自分の弱さや不安をさらけ出すたびに、この感情が読者の中に芽生えることが多いんですね。
藝大試験の前夜。八虎が「自分には才能がない」「何も描けていない」と泣き崩れる場面では、「昔の自分と重なる」「直視できない」といった声が多く上がっています。
あまりにもリアルだからこそ、心が揺さぶられるのです。
もうひとつが「投影」です。これは、自分の過去の経験や未解決の感情を、無意識のうちに登場人物に重ねてしまう心理作用を意味します。
「努力しても報われなかった」「進路のことで親と揉めた」といった経験がある人ほど、八虎や龍二の姿に強く反応してしまう傾向があるんですね。



自分の経験と重なると、よりしんどく感じるんですね…。



そうなんです。作品の中に自分を見てしまうと、単なる“他人の物語”ではなくなります。その分、精神的に疲れたり、強い違和感を覚えることがあるんです。
こうした心理的な反応は、作品のクオリティが高いことの裏返しとも言えます。
でも同時に、「疲れる」「しんどい」と感じさせる要因にもなってしまいます。
つまり、自分の過去の体験によって、作品の受け取り方がまったく変わってくるんです。
価値観ギャップと文化的背景



芸術の世界って、正解がないからこそ受け入れにくいのかもしれませんね。



その通りです。「正解のない評価」や「努力しても報われない世界」は、日本的な受験文化とは真逆で、違和感を感じやすい構造になっています。
「ブルーピリオド」が理解しにくいと感じられる背景には、読者の中にある価値観とのギャップが大きく関係しています。
「芸術って結局センスの世界でしょ?」「努力が報われないのは納得できない」という気持ちが強い人ほど、この作品の世界観に戸惑いや違和感を抱きやすいんです。
藝大入試は専攻ごとに基準が異なるが、一般的には完成度だけでなく発想や表現意図が重視される傾向がある。
一般的な学力試験とは評価の軸がまったく違うため、「こんな絵で評価されるの?」という疑問が出てくるのも当然なんですね。
八虎が全力で描いた絵があっさり否定され、「で、何を考えて描いたの?」と問われる場面は、その象徴です。
日本の受験文化では「毎日コツコツ努力すれば報われる」という価値観が根強くあります。
そんな中で、「正解がない世界」で努力が通じない場面に直面すると、違和感が強くなるのは自然なことかもしれません。
「美術の試験で泣くってどういうこと?」と感じる人がいるのも、こうした背景があるからなんです。
美大予備校や藝大独特の空気感も、未経験の人には“閉じた世界”に映ります。
登場人物たちがぶつかり合いながら制作し、講評では専門用語が飛び交う。そんな描写に「自分とは別世界」と感じ、距離を感じてしまう読者もいます。
この作品を理解するには、「芸術という文化」や「評価基準の違い」といった背景知識が大きく影響します。
知らないまま読むと、そのズレが「気持ち悪さ」や「ついていけなさ」につながってしまうんです。
読者タイプ診断:自分がどの「違和感タイプ」か診断して入口を選ぶ
「ブルーピリオド」に違和感を抱く理由は、本当に人それぞれ。
だからこそ、自分に合った“入り方”を見つけるだけで、ぐっと見やすくなることもあります。
このセクションでは、いくつかの質問に答えるだけで、あなたにぴったりな視聴・読書スタイルがわかります。



自分がどのタイプかわかれば、作品の楽しみ方も変わりますか?



はい、違和感のポイントは人それぞれなので、自分の特性を把握できると「そのせいだったのか」と腑に落ちて、より快適に作品と向き合えるようになりますよ。
簡易チェックリストと推奨入口



まずは自分の傾向を知りたいです。どんな質問があるんですか?



以下の4つにYES/NOで答えてみてください。あなたがどんなタイプか、すぐにわかります。
まずは以下の4つの質問に、YESかNOで答えてみてください。
Q1:感情移入しやすく、人の葛藤に敏感だと思う?
Q2:受験や進路で、過去に深く悩んだ経験がある?
Q3:芸術や美術に少しでも触れたことがある?
Q4:作品は短時間でサクッと楽しみたいほう?
この答えをもとに、あなたのタイプとおすすめの入口をチェックしてみましょう。
| タイプ | 特徴 | おすすめ媒体 |
|---|---|---|
| Aタイプ | 芸術共感型(YESが多め) | 原作からの読破がおすすめ |
| Bタイプ | ライト視聴型(Q4がYES) | アニメから入るのが◎ |
| Cタイプ | 感受性強め&短期集中派(Q1とQ4がYES) | アニメを1話ずつ小分けに観る |
| Dタイプ | 映画好き・時間がない派(YESが少なめ) | 実写版+原作名場面ダイジェスト |
途中で「ちょっとしんどいかも」と感じたら、無理せずスタイルを変えるのもひとつの手です。
たとえば、原作なら好きなキャラのシーンだけ拾い読みしたり、アニメは1話飛ばしてみたり。作品との“ちょうどいい距離感”を見つけてくださいね。
見る・読む際のメンタルケアと休憩ポイント



続けて観るのがつらくなったらどうしたらいいですか?



無理せずに自分のペースを尊重することが大切です。少し立ち止まったり、工夫して観ると気持ちに余裕ができますよ。
「ブルーピリオド」は、感情描写や葛藤の表現がとてもリアルな作品です。
そのため、人によっては心理的に“重たい”と感じる場面も多いんですね。
そんなときに大切なのが、無理せず向き合うためのメンタルケア。ここでは、媒体別に取り入れやすい工夫を紹介します。
アニメを観るときに効果的なのが「音量調整」。劇伴やモノローグが感情に深く刺さりすぎるときは、少し音を下げるだけでも気持ちがラクになります。
1話ずつ間を空けて視聴する「分割視聴」もおすすめです。とくに第5話のような重たいエピソードは、翌日に続きを観るなどの工夫で、感情の負担を軽減できます。
原作漫画の場合は、「注釈付きの読み方」が役立ちます。ネットの解説記事やブログと一緒に読むことで、「なぜこのキャラがこう動くのか?」が理解しやすくなります。
とくに大学編のように登場人物が多くなるパートでは、人物相関図を手元に置いておくだけで、読みやすさが格段に変わりますよ。
実写映画では、「前もって見どころを知っておく」のがポイント。
ダイジェスト動画やレビューで全体像を把握しておくと、物語の展開がわかりやすくなり、心理的な負荷も減ります。
観終わった後にSNSや感想記事を読むのも、気持ちを整理する助けになります。
どの媒体でも共通するのは、「自分のペースを守ること」と「一度立ち止まる勇気」です。「しんどいけど気になる」そんなときこそ、自分に合った方法で作品と向き合ってみてください。
実用:違和感を和らげて楽しむ具体テク&見る順
「ブルーピリオド」に“気持ち悪い”や“しんどい”という印象を抱いた人も、ちょっとした工夫次第で作品を楽しめるようになるかもしれません。
媒体ごとに違和感の出やすいポイントを避けたり、見る順番を変えたりするだけで、ぐっと入りやすくなることもあるんです。
このセクションでは、具体的な楽しみ方のコツを紹介します。



ブルーピリオドをもっと楽しめる方法ってありますか?



違和感を感じる方でも、視聴・読書スタイルを少し工夫することで、より快適に楽しめるようになりますよ。
媒体別に有効な“楽しむコツ”



どの媒体から入るかで違和感の強さも変わるんですか?



はい、原作・アニメ・実写それぞれの特性を活かせば、スムーズに楽しめる方法があります。
まず原作マンガで違和感を軽減するには、「名場面・名言」から読むのが効果的です。
たとえば、八虎の合格シーンや、佐伯先生の印象的なセリフなど、感情のピークに触れておくことで、物語全体がすんなり入ってきます。
そのうえで全巻を読むと、感情移入しやすくなるでしょう。
アニメ版の場合は、「1話完結感のあるエピソード」から観るのがとっつきやすい方法です。
第1話や第4話などは構成がシンプルで、キャラクターの感情も整理されているため、初見でも理解しやすくなっています。
演出の“圧”が気になる場合は、字幕をオンにしたり、音量を控えめにしたりするのも効果的。モノローグの刺さり方を和らげる助けになります。
実写映画は、「ダイジェスト的に世界観を味わう」というスタンスで観ると良いでしょう。
あらかじめ「原作とは別物」と捉えることで、演出の軽さやキャラ設定の省略も受け入れやすくなります。
とくに美術作品の映像化や音楽面には独自の魅力があるので、そこに注目することで、原作とはまた違った楽しみ方ができます。
あらかじめ「違和感が出やすい場面」を避けるのもひとつの手です。
たとえば、大学編の群像劇的な描写が苦手な人は、藝大受験編までを中心に読むのもアリ。自分に合った“心地よいブルーピリオド”の体験スタイルを探してみてください。
よくある誤解と反論



「急にうまくなりすぎ」って思うのは変なんでしょうか?



自然な感想です。ただし、それも“象徴表現”や“物語上の演出”として意味があるんですよ。
「ブルーピリオド」に対する否定的な声としてよく挙がるのが、「こんな短期間で絵がうまくなるわけがない」「演出がわざとらしくてリアリティがない」といった意見です。
たしかに、美術や藝大受験に馴染みのない読者にとっては、八虎の成長の速さやキャラクター描写に違和感を覚えるのも無理はありません。
これらには“作劇上の意図”や“象徴的な表現”が含まれていることを忘れてはいけません。
たとえば、八虎の急成長は「内面の変化」を描くための象徴表現として描かれている側面があります。
作者自身の実体験や観察に基づいていて、単なるフィクションではなく、「自分を見つめ直す過程」として物語が進んでいるんですね。
「演出が過剰すぎる」「キャラが極端すぎる」といった批判も、一種の時代性と関係しています。
SNS時代の今は、共感性羞恥に敏感な人や、心理描写の濃さに疲れてしまう読者が増えてきました。
以前なら普通に受け止められていた描写が、“やりすぎ”と感じられることもあるんです。
大切なのは、「なぜこう描かれているのか?」という背景に目を向けてみること。
そうすることで、最初は納得できなかった部分にも、新しい意味や魅力が見えてくるかもしれません。
issyによる『ブルーピリオド』の深層考察:「気持ち悪い」と感じさせるリアルの罠


「ブルーピリオド」が“気持ち悪い”って言われるのは、キャラがウザいとか展開が急すぎるから…だけじゃないんだよな。
むしろ、それが“意図された表現”だったとしたら?
作者・山口つばさは、あえて“感情移入できない構造”や“心理的な負荷”を作ることで、読者に「安全圏からの読書体験」を壊しにきてる可能性があるんだ。
この記事でも紹介されてた「共感性羞恥」や「投影」といった心理的メカニズムも参考にしながら、ここではもっと「作者の視点」や「表現技法の意味」にガッツリ迫っていくぜ!
生々しすぎる八虎の描写は「分断された自我」を意図してる?
記事でも出てきたけど、八虎ってマジでリアルに葛藤しすぎなんだよな。
泣く、悩む、吐く、叫ぶ……その一個一個が“見てるこっちが恥ずかしくなるレベル”ってワケ。
でも、これって「共感性羞恥が強いから」だけじゃなくて、八虎自身が“自分の中にある理性と衝動のズレ”を体現してる存在だと捉えると、めちゃくちゃ腑に落ちる。
たとえば、藝大を目指すって決めたのに「やっぱ無理かも」「自信ない」「才能ない」って自己否定を繰り返す姿。
これは“意志”と“感情”が噛み合ってない証拠でもあるんだよな。
で、そんな彼の揺れが、読者の中にある未整理の自分を無意識に刺激してくる。
八虎って、実は“読者の中にある未完の自我”の投影先になってる可能性すらあるってワケ!
「描写が濃すぎる」=「読者との心理距離をあえて縮めてる」演出トリック
アニメや実写で「演出が濃すぎる」って声が出るのも、実は計算された“没入妨害装置”って考えるとかなり面白い。
アニメでの激しい色彩変化や、実写での感情の詰め込み不足――どっちも「見てる側が気持ちを整理しきる前に、次々に感情情報が押し寄せてくる」構造になってるんだ。
つまりこれ、“視聴者の心理的防御”をぶっ壊す演出ってワケ。
ブルーピリオドは「物語を眺める」じゃなくて、「物語に晒される」体験を目指してるんだよな。
山口つばさ、マジで“絵の中に入り込むとはどういうことか”っていうのを、読者自身の身体感覚で味わわせようとしてるっぽい。これはなかなか大胆すぎ!
「気持ち悪さ」は“芸術を理解する痛み”そのものだった?
最終的に、「ブルーピリオドが気持ち悪い」って感想の正体ってさ、“芸術を理解しようとするときに発生する痛み”そのものなんじゃないかと思うわけ。
八虎が描くことに迷うとき、龍二が性の在り方に悩むとき、世田介が誰ともつながれないとき――どれも「表現とはなにか?」っていう問いとガチで直結してんだよね。
そして読者は、知らないうちにその問いに“巻き込まれてる”。
「絵を描くってことは、心をさらけ出すことだろ?」って、問われてる気分になっちまうんだよな。それが刺さる。
リアルすぎて、逆に「気持ち悪い」って反応になる。
でもこれってつまり、「創作という行為の本質に、読者が触れちゃった証拠」なんじゃね? だからこの“気持ち悪さ”は、実はブルーピリオド最大の武器でもあるってワケ!
「“気持ち悪い”って思っちゃった自分、間違ってない。でもそれ、作品の狙い通りかもよ?」
ブルーピリオドは“痛みをともなうアートの旅”。その痛みを味わえる読者は、ある意味で一番深く作品と向き合えてる読者かもしれないぜ!
よくある質問
- ブルーピリオドの作者は女性ですか?
-
はい。作者は山口つばさで、日本の女性漫画家です。
- ブルーピリオドの作者は藝大出身?
-
はい。東京藝術大学・油画専攻に現役合格し、同大学を卒業しています。
- ブルーピリオドは何巻で完結しますか?
-
2025年8月現在もアフターヌーン連載中で、完結の公式発表はありません。
- ブルーピリオド 実写のキャストは誰?
-
2024年公開の映画版は、眞栄田郷敦・高橋文哉・板垣李光人・桜田ひよりらが出演しました。
ブルーピリオドが気持ち悪いと言われる理由のまとめ
「ブルーピリオド」が“気持ち悪い”と感じられるのは、ただの好き嫌いでは片づけられません。
そこには、リアルすぎる描写、感受性の違い、媒体ごとの演出の差といった、複雑な要素が絡み合っています。
生々しい心理描写や芸術特有の評価軸、キャラクターの強さや演出の濃さが、「共感性羞恥」や「感情の投影」といった心理メカニズムを通して、読者に“違和感”として突き刺さるんです。
そしてそれは、原作・アニメ・実写といった媒体ごとに見え方も変わるため、「どれが自分にとって合わないのか」も人それぞれ。
この記事では、そんな違和感の正体を段階的に整理しながら、読者が自分に合った視聴・読書スタイルを見つけやすくなるよう導いてきました。
「なぜか苦手だった…」というモヤモヤが、「あ、こういうことだったのか」と腑に落ちたなら幸いです。
あなたにとっての「ブルーピリオド」との向き合い方が、少しでも快適で豊かなものになりますように。



結局、ブルーピリオドが「気持ち悪い」って感じるのはどうしてなんですか?



主な理由は、リアルな心理描写が読者の感情を強く刺激するからです。特に「共感性羞恥」や「投影」といった心理的要素が絡むことで、“読んでいてしんどい”と感じる人が多いんですね。


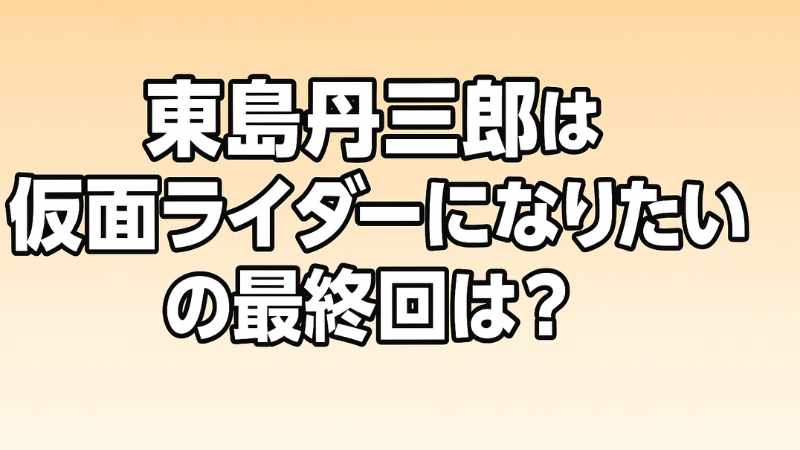
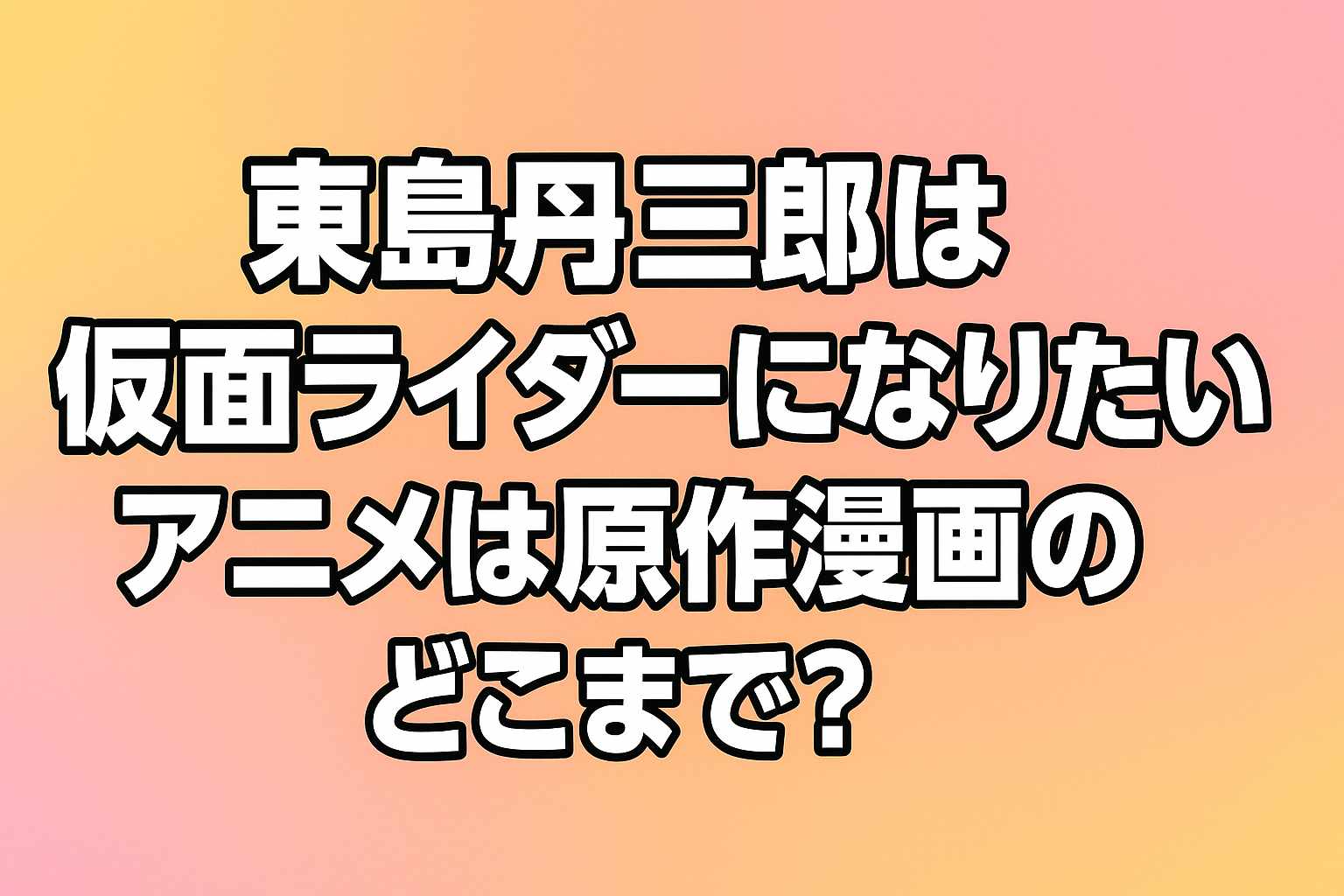
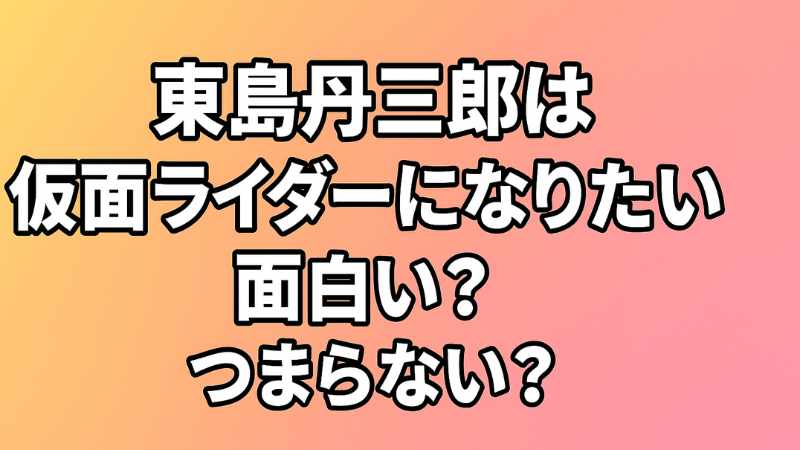
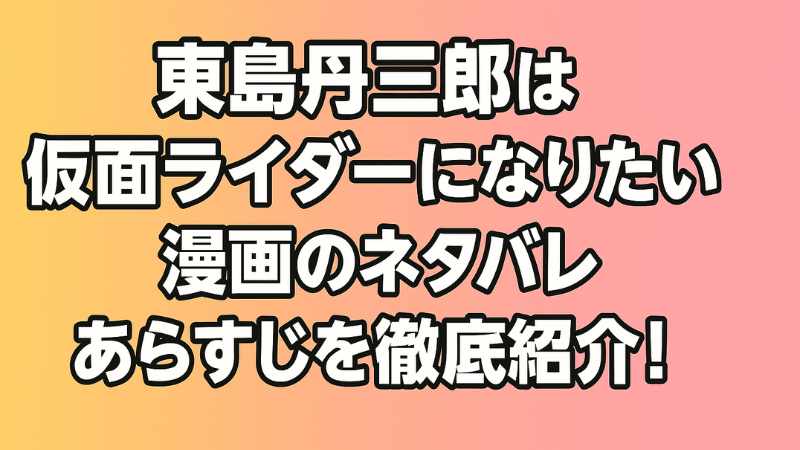

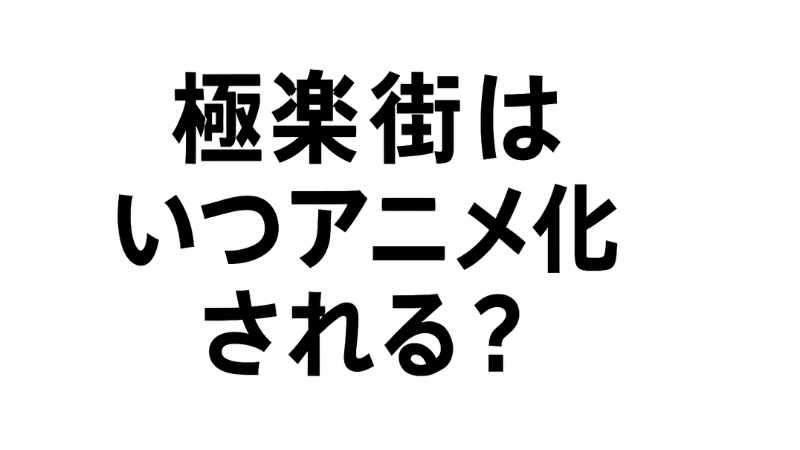
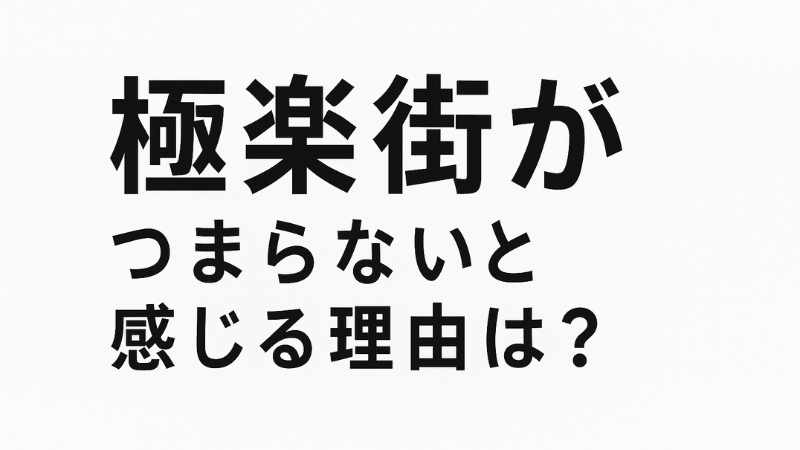

コメント